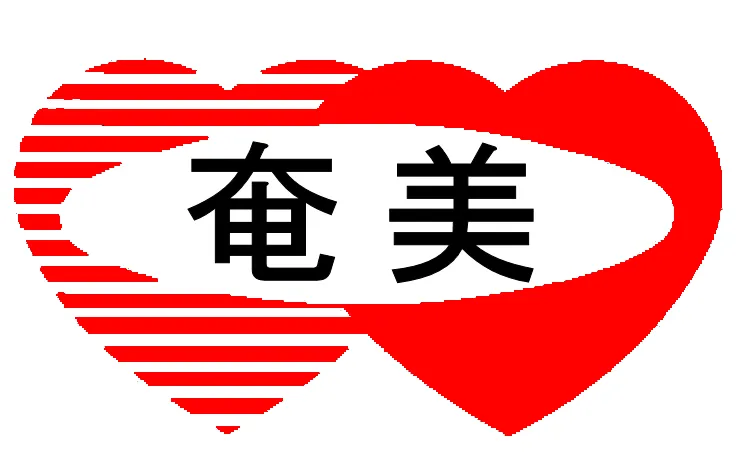- 更新:2025年10月03日
【11/9(日)まで募集中】『AI・IoTが拓く建設業の未来~災害予兆と資材管理の実現~』~STARTUP YAMANASHI OPEN INNOVATION PROGRAM 2025~
湯澤工業株式会社

- ゼネコン
- 道路工事
- リサイクル
- 中小企業
プロジェクトメンバー
責任者
プランのアップグレードで企業責任者情報を確認いただけます
プラン詳細はこちら
自社特徴
湯澤工業は昭和33年の創業以来、土木工事を中心に地域インフラの整備や災害復旧を担い、人々の安全と暮らしの質向上に貢献してきました。「POWER TO THE PEOPLE」を掲げ、建設業を通じて土だけでなく人の心も動かす企業を目指しています。近年はICT施工やドローン測量、BIM/CIMなどデジタル技術の導入、若手技術者の育成や技能継承にも積極的に取り組み、建設業の魅力向上に挑戦しています。地域に根ざした確かな技術力と現場経験を活かし、社会的価値ある建設業を未来に繋げていきます。
提供リソース
・年間20か所程度の建設現場を活用した実証フィールド
・現場経験豊富な社員による施工ノウハウの提供
・護岸工事・災害復旧工事の知見、重機・測量器械
・コンクリート破砕・木質ペレット製造設備
・自治体や地域企業とのネットワーク、連携実績
・現場データや施工実績を活かした社会実装力
解決したい課題
共創テーマ①『護岸工事の知見を活かした次世代防災ソリューションの実現』
護岸工事や砂防工事で培った土砂災害リスク判断のノウハウと、気象データ・IoTセンサー・AI解析などと組み合わせ、災害予兆をリアルタイムに把握する仕組みを開発していきたいです。現場データを活用し、危険箇所の早期発見や施工計画の最適化、自治体や住民への迅速な情報提供を実現することで、地域の被害軽減と安心を支える次世代防災ソリューションとして、全国展開可能な新しいソリューションを目指します。
共創テーマ②『建設現場における資材管理の見える化と行動変容の実現』
ドローン、IoT、AI解析など先進技術を活用し、資材管理の“見える化”を推進
していきたいです。また、従業員の作業行動や資材利用の改善につながる仕
組みを構築し、単なるデジタル化にとどまらず、行動変容を促す教育・運用
設計も実施。施工効率や安全性の向上、技能継承強化につなげるパートナー
企業を募集します。
共創テーマ③『地域資源で創る、循環型社会の未来モデル』
パートナー企業と共に、コンクリート廃材や木くずの新たな用途や加工技術を共創し、地域内での循環利用を推進します。再生資材や再エネ活用による脱炭素・コスト削減を両立させつつ、廃棄物ゼロを目指す仕組みを試行。得られた知見は、同業他社や自治体にも展開可能な地域モデルとして社会に広げ、持続可能な経済循環の実現に貢献します。
共創で実現したいこと
護岸工事や砂防工事で培った土砂災害リスク判断の知見を軸に、気象データやIoTセンサー、AI解析などの先進技術を組み合わせ、地域の災害予兆をリアルタイムに把握する次世代防災ソリューションを共創したいです。また、施工現場のデジタル化による効率化や安全性向上、現場データの教育・技能継承への活用も進め、地域の安心・安全と建設業の持続可能な成長を同時に実現したいです。パートナー企業と共に、全国展開可能な新たな価値を生み出し、地域社会全体にワクワクする未来を届けることを目指します。
求めている条件
・災害リスク解析・予測:AI/機械学習による土砂災害・洪水リスクの予測
・センサー・IoT活用:河川・護岸のリアルタイム監視、データ取得システム
・現場管理デジタル化:データ可視化ツール/ダッシュボード設計・UX設計
・施工効率化支援:ドローン・ロボティクスによる現場観測・施工補助
・教育・技能継承:現場データ活用による技能継承・研修プラットフォーム