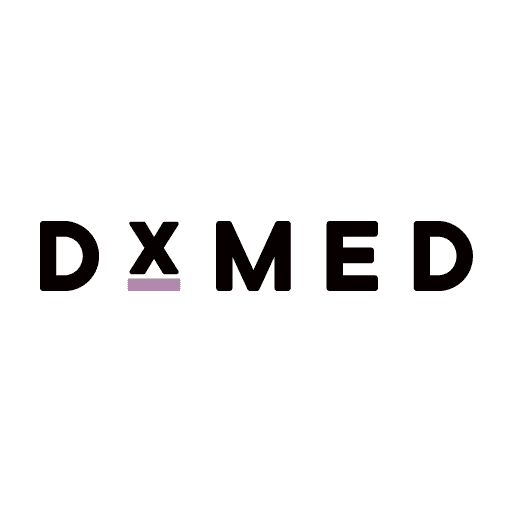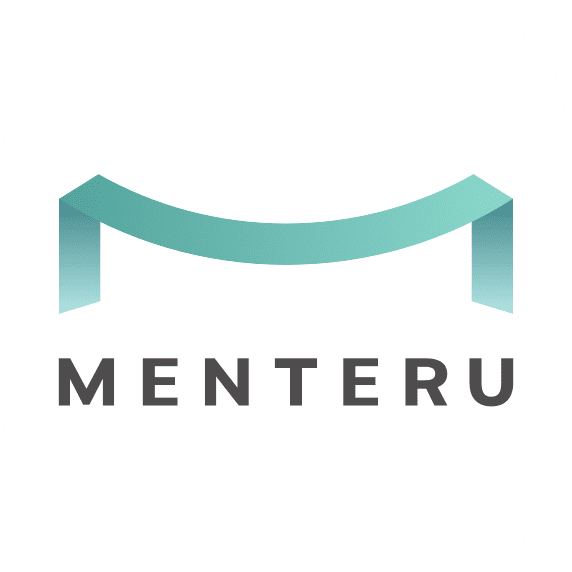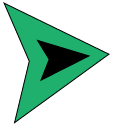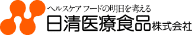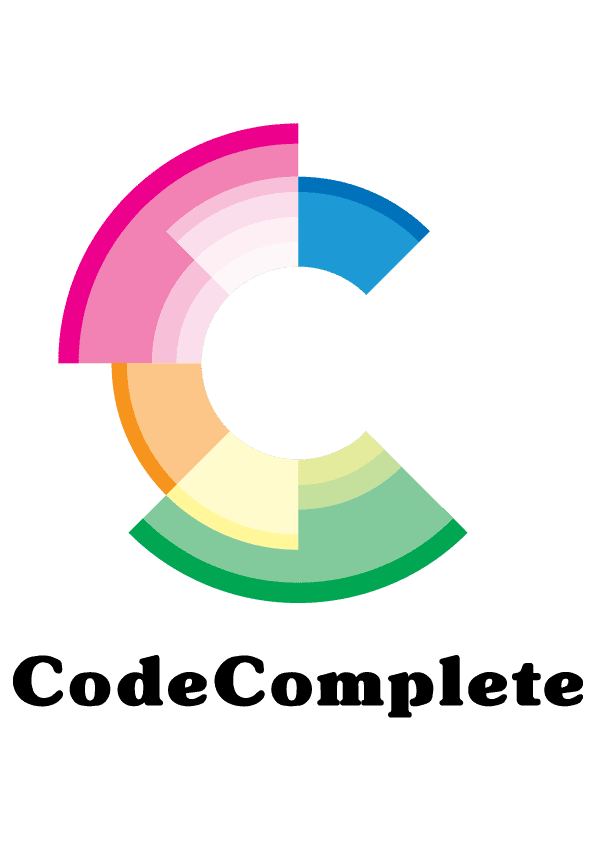- 公開:2020年06月24日
- 更新:2022年03月09日
vol.12 AUBA活用事例インタビュー 他社連携で生まれた事業をさらに発展させるためOIを推進!/株式会社AwesomeLife
株式会社AwesomeLife

- ヘルスケア
- 介護
- 遠隔医療
- センシング
- パワーマネジメント(省電力、長寿命)
- アクチュエータ
- リソース提供(既存技術の提供・特許流用の検討など)
- リソース探索(技術・アイディアなどを探したい)
- 既存プロダクト改善(生産プロセス・製品性能・システム)
- 事業提携
- 資金調達したい
- アイディアソンの実施
- 新市場の模索
- 中小企業
- スタートアップ
こんにちは!AUBA ビジネスコネクティングチームの栗山です!
AUBA(旧eiicon)ご活用の参考となる事例をお届けするこのブログ、本日は活用事例の第12弾をお届け致します。
今回は他社との連携で生まれた事業を更に発展させ、
テクノロジーで介護現場の課題解決を目指すこちらの企業をご紹介!
■株式会社AwesomeLife
※AUBA利用歴6か月/コンタクト実績16社/面談5社/提携検討中 3社
https://auba.eiicon.net/projects/17760
ー本日お話を伺うのは株式会社AwesomeLife 代表取締役 田中一秀様です!よろしくお願い致します。
どのような背景で他社との共創、オープンイノベーションに取り組もうと思われたのですか?
弊社は医療・介護現場のIT化を支援するコンサルティングや、介護施設の職員向けに遠隔でリハビリの指導をする、「遠隔リハビリテーション指導サービス」の開発を行っている会社となります。元々は介護事業をメインに事業を展開していたのですが、医療・介護の現場はIT化が遅れている分野であり、現場自体をアップデートするためのコンサルティングや遠隔サービスの開発、介護ロボットのコンサルティング等、事業の幅を広げていきました。
特に遠隔リハビリテーション指導サービスの開発はNEC様との業務提携により5年程前から進めていたプロジェクトとなり、今年に入りようやくサービスローンチできたものとなります。
このサービスは様々な横展開が可能で、幅広い企業にご活用いただけるものと考えています。
本事業のメインターゲットとなる介護領域以外のところにもこのソリューションが提供可能なマーケットは存在していると考えており、より多くの企業様へのサービス提供を模索するべく、サービスのブラッシュアップやさらなる展開の可能性を様々な企業様と共に探っていければ、と思いパートナーの探索を始めました。
そんな折に知人がFacebookでAUBAについて共有していたのを拝見し、登録した形です。
ーなるほど。現在の事業のさらなる展開の一手段としてオープンイノベーションに取り組もうとされたということですね!
実際に今回幅広い分野に横展開していきたい、と伺っている遠隔リハビリテーションサービスも、NEC様との業務提携により開発されたものということですが、こちらについてあえて他社との共創を選んだ理由はありますか?
自分たちの力を発揮できる場所に専念したいからです。我々理学療法士はリハビリテーションそのものに関しては高い専門性を持っています。しかし、システムの構築などといった別分野の話になったとき、我々に知見はあまり無い状況です。そうしたものを自前で作るよりも他社と提携したほうが確実で早いですし、我々も自分たちの分野に専念することができます。
NEC様とは今回の「遠隔リハビリテーション指導サービス」事業でしっかりと提携しており、関連人材の育成にもご協力いただいております。その人材を本業である介護領域にしっかりと活かすこともさることながら、幅広い体験と経験を積むことでこの「遠隔リハビリ」における専門職を構築できると考えています。この人材を含めた新たなソリューションの横展開を狙っているというところです。
ー自社と相手企業の、お互いが持っている強みを有効活用しようと考えているということですね。自分の専門分野に専念することでより力を遺憾なく発揮できるかと思われます。また、他社連携で既に事業が生まれているところにさらに発展性を持たせるためにパートナーを探す、というのも非常に面白いですね。実際にAUBAをご活用いただいていかがですか?
16社にメッセージを送り、5社から返信をいただきました。
そのうち3社と面談が決まり、2社と共創に向けて検討中です。
具体的には遠隔リハビリテーションの実現化に向けたシステムやアプリ開発、さらに当社サービスの具体的な発展に向けてのアドバイスや共創の可能性を模索している状況となります。
ー既に前向きにご検討いただいている企業様がいらっしゃるとのこと、ありがとうございます!
コンタクト企業は実際にどのように検索して探されましたか?
フリーワード検索で「遠隔」「リハビリテーション」「ヘルスケア」と検索してみたり、メルマガで届くおすすめ企業特集から選出していました。
具体的には「ヘルスケア特集」を参考にしており、ヘルスケアとは様々な領域がありますので、当社の持ち得ているソリューションを活かしていただけるような企業様を中心にお声掛けさせていただきました。全く畑違いのところも、少しでも重なる部分があればご連絡し、可能性を模索し、さらにビジネスモデルの昇華を行っています。
ーおすすめ企業の特集はカスタマーサクセスチームが返信率や直近のアクティブ度等総合的に判断して選出しているものになります。企業選出にお悩みの方は是非ご参考いただけると嬉しいですね!
特集や検索結果の中から実際にメッセージいただいているとのことですが、アプローチする基準、のようなものはございますか?
PRページの「一緒に何をしたいか」の項目が具体的に書いてあるか、という点を注視しています。目的が明確じゃない企業様とお話する場合、面談に至ってもなかなかゴールを見据えた話がしにくく、逆に目的が明確な企業様とは互いに目的のすり合わせをし、一致すれば進む、一致しなければ進まない、とネクストステップも明確でスムーズに共創を進めることができると考えています。
この他社様のPRページを見る際の判断ポイントは他社様が弊社のページを見る際にも同じ様に判断されるのだろうと感じています。
そのため、自社のPRページを作成する際も「一緒に何をしたいか」は「◯◯年に◯◯を実現したい」といった形で時期とやりたい事を明確に記述するよう心がけました。
ー他社のPRページを見る際の印象やポイントを自社のPRページ作成に活かすというのは非常に重要なポイントですね!AUBAは14,000社以上の企業が登録されているプラットフォームですし人気の企業様は50以上ものメッセージを受け取られます。こちらからアプローチし返信をもらうにせよ、メッセージを受信するにせよ「選ばれる」PRページを作成する必要があります。
既にAUBAで出会われた企業様と共創に向けてのお話をスタートされているとのことですが、何か取り組む中で課題に感じられている部分はありますか?
どこまで自社の情報を共有して良いのかは非常に悩みました。持っている技術や知識をどこまで共有していいのか、また先方にどこまで理解いただけるのかかわからないという中でプレゼンするのは不安に感じることも多々あります。また、プレゼンの結果弊社との共創という形を選ばれず、アイデアだけ取られてしまうのはないかと不安になることもありました。
よって積極的に興味を持っていただけた場合には、NDAを締結するようにご依頼させていただき、資料もお渡しできるものと、難しいものにと分けて対応しております。そもそもこれらの面談で簡単に盗用されるアイディアなど、誰でもできるものですし、そこまでシビアに考えなくてもよいかもしれないとも、最近思い始めています。
ーなるほど。共創はお互いの強みを活かす取り組みであるために、どこまで情報提供すべきなのか悩みますよね。
新型コロナウイルスの影響でオンライン面談の機会も増えたかと思われますが、コロナ以前と比較し、何か影響を受けたことはございますか?
弊社が取り組んでいる事業が元々「遠隔リハビリテーション指導サービス」なので事業そのものにあまり影響はないのですが、商談を全てオンライン商談に切り替えたのは始めてだったので、試行錯誤しながらやっている状態です。
対面での商談だとお互い気を使って社交辞令的なやり取りも多くなるかと思うのですが、オンラインだとニーズがマッチしない場合はすぐにお開きになったりと、対面で会うよりビジネスライクな印象を受けます。
必要な部分だけ話して終わる、という形に自然となりやすいので、それはそれでいいのかもしれない、と思っているところではあります。
ーオンラインに切り替えたことにより生まれたメリットもあるということですね。今後はオンラインと対面での面談を適宜使い分けていく文化になるとより地域の垣根無くオープンイノベーションを推進できるのでは、と思います。
最後に、今後の展望をお聞かせ頂けますか?
弊社はテクノロジーで介護現場の課題解決を試みていますが、開発側は現場を知らず、現場側はITリテラシーが低いため双方の理解が進まず、結局のところ課題解決に至ることができない、というジレンマがありました。
理学療法士を持っている介護のプロである我々が「遠隔リハビリテーション指導サービス」の開発をしているのはこのギャップを埋めるためです。
今後は世の中の介護ロボットを紹介するポータルサイト等も開発し、最終的には「遠隔リハビリテーション指導サービス」での職員への指導時に、指導をロボットで補えるような仕組みを構築していきたいと考えています。
コロナの影響もあり医療現場での遠隔診療も進んできたので、リハビリ業界の遠隔化に寄与すべく様々な共創を進めていけたらと考えています。
ーレガシーな部分が多々ある領域だからこそ、他社と共創することによって可能になることが多々あるということですね。
本日は生の声をお聞かせ頂き、ありがとうございました!
※※今回ご紹介した企業にご興味頂いた方は是非以下よりコンタクトが可能です※※
https://auba.eiicon.net/projects/17760
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
【共創状況報告にご協力頂いた方へ、メッセージチケットプレゼント!】
AUBAでは実際に他社様とお会い頂き、提携検討フェーズに進まれている方を対象に、共創状況のヒアリングをさせて頂いております。
提携に向けて2回目の商談が決まった!という段階から、実証実験に向けて進んでます!等、お聞かせ頂ける範囲でお答え頂けますと幸いです。
https://eiicon.net/forms/contact
------------------------------------------------------------
AUBA活用についてお困りの方は是非ビジネスコネクティングチームにご相談ください。
PRページの書き方からコンタクト先の探し方、合いそうな企業の見つけ方が分からない!等、
些細なことでもお気軽にご相談くださいませ!
問い合わせ先:cs@eiicon.net