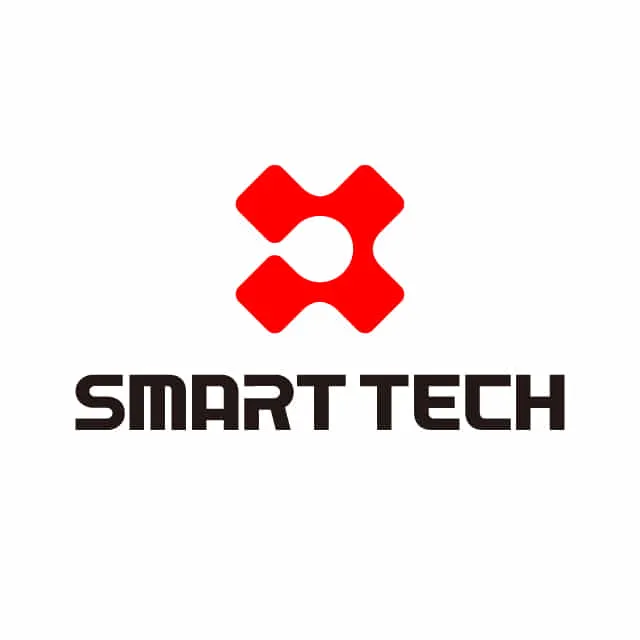- 更新:2024年10月12日
独立に進められた、原子炉、核融合、高エネルギー加速器、水素、宇宙航空技術等が、その成果を持ち寄って新しいエネルギー生成供給技術を確立するプロジェクト。 それぞれの長所がそれぞれの短所を解決し、実績のある既存技術の組みあわせで、環境と安全性を高次元で両立させる、 もって、人類のエネルギー問題を解決子、文明の持続発展を願う。
(株)Fusion Fission Powers
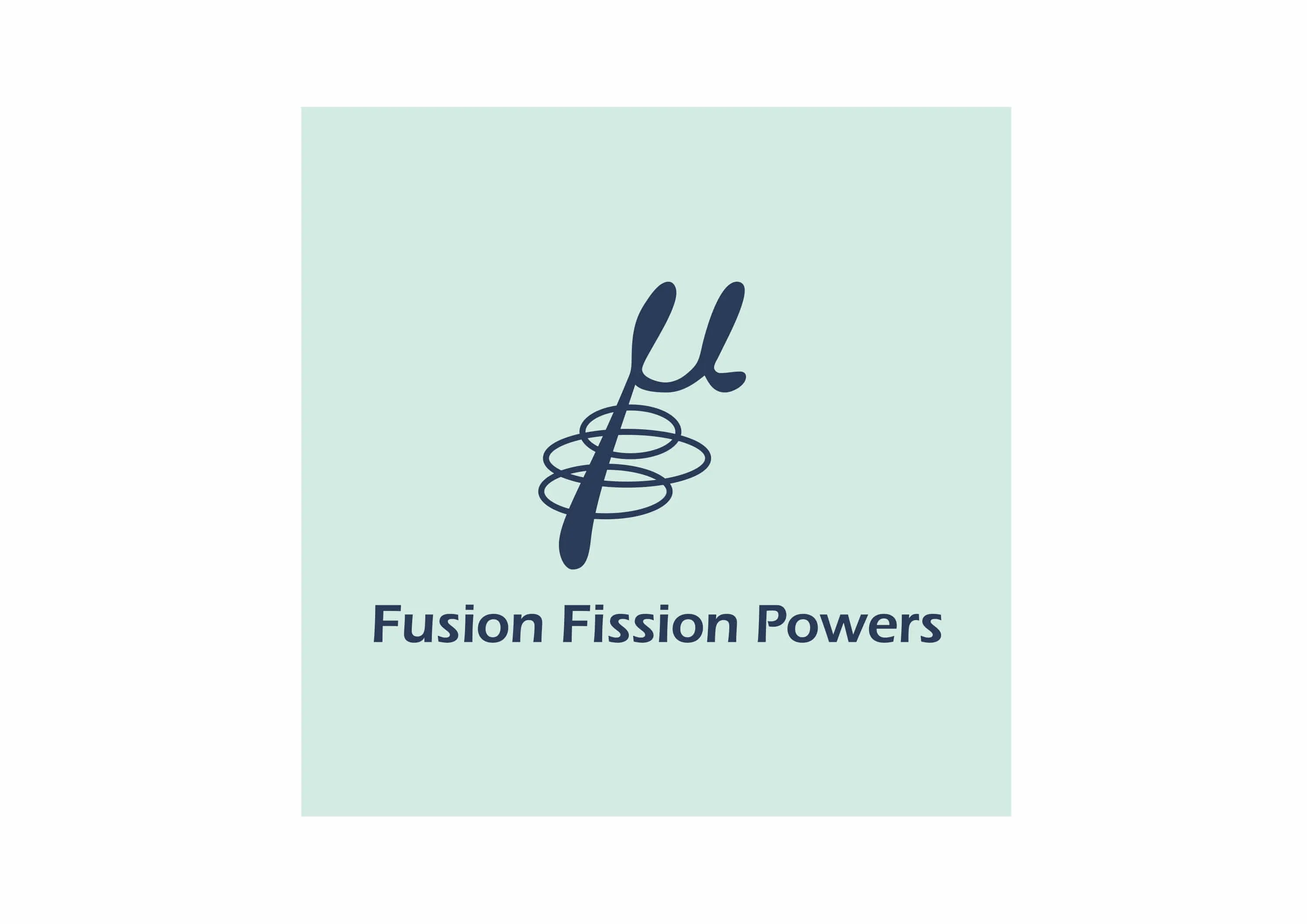
- プロダクト(製品)共同開発
- 事業提携
- ジョイントベンチャー設立
- 資金調達したい
- 新市場の模索
- 3カ月以内の提携希望
- 地方発ベンチャー
- 6カ月以内の提携希望
- 教育研究機関
- スタートアップ
プロジェクトメンバー
責任者
プランのアップグレードで企業責任者情報を確認いただけます
プラン詳細はこちら
自社特徴
【自社特徴】核融合研究の成果を活かし、安全でクリーンな未臨界トリウムエネルギー源を実現する開発会社。
既存の概念、既得権益や柵に囚われない、自由な発想。
【事業・資金計画】
1.2028年 炉芯原理実証(10kW)デモ、2030年 1MW炉試作、2035年10MW実証炉デモ 2035年50MW炉社会実装
2. 2028年 株式公開予定、 2030年 第1回増資 50億円 2035 年 第2回増資
【価格】
3. 標準機種・価格 50MW / 基 1000億円/基 (2024年時点での推定)
【市場】
4. アフリカの人口40億人、人口10万人程度の中小都市、電力需要量0.5kW/人(日本の約40%)で、4万台、4兆円。
5. 都市間広域送電ネットワークが不要、地産地消型電力供給設備、廃熱で海水淡水化(沿岸部)および排水浄化(内陸部)も一括。
提供リソース
1.核融合駆動ー未臨界トリウムエネルギー源の実証・社会実装に伴う投資情報、知財(特許等)の共有
特許1 特願2014-146285(2024年8月28日)(核融合駆動ー未臨界トリウムエネルギー元の原理特許、および実施方法について記載)、特許2 WO2023162286号公報、特許3 JP 2013-11384 A 2013.1.17、他多数
2.Wide Band Gyap SiC Wafers 製造技術開発への応用:
本研究開発の最も重要な点は、従来とは異なる炉心構造、即ち原子燃料を細さや化に詰めて、この鞘管を未知に連立させ、その隙間を冷却水、又はこうあるヘリウムガスでれいきゃくしていた、。本発明では、燃料自体が、蜂の巣状の薄い膜状に形成され、その案お腹をヘリウム窓の高圧ガス画循環する。この方式は、自動車の排ガス化の中に設けられている触媒フィルターと同じであり、耐久性、耐振動性、耐衝撃性に優れており、原子炉に用いれば、著しく耐震性を向上させる。232ThO2のによる2800℃焼結温度は、2800℃を越えるため、従来の電気釜やガス釜に変わる新しい加熱炉が必用になる。我々は、電子レンジの原理を応用した、マイクロ波焼成炉を開発した。このマイクロ波炉は、現在緊急に求められているSiCのWide band gyap 半導体に市場に投入する。予想される開発資金は5億円程度、販売数は10000セット、単価5千万円を見こんでいる。この開発を機に、株式公開に踏み切る予定である。
解決したい課題
以下に解決したい技術課題を示す
A.小型核融合炉要素部
1.重粒子重陽子加速器:仕様 電圧200MeV〜400MeV. 粒子数 10^12 /s, 方式 医療用小型重粒子線加速器 + FFAD等ブースター
2.可搬型、大出力レーザーの調査・開発。用途はレーザー駆動ミュオンソース(DARPA公募あり)
3.IEC (Inertial Electrostatic Confinement ) DD中性子源:実験用可搬型小型中性子源、(2024年).
4.循環型超音速風洞型核融合炉心の設計・試作・開発:流路中にラバールノズル及びマッハ衝撃波による高圧ガス淀み点形成。
最高流速:マッハ7 最高密度:4x10^22/cm3、試験ガス:重水素5. ミュオン生成部 設計試作:(2024〜2030年度)
B.未臨界トリウム核分裂炉
1.核分裂炉心設計用シミュレーションコードの開発:既に実績のある米国DOEのShippingport Atomic Station の未臨界トリウム炉を計算機上に再現し、核分裂反応と中性子拡散過程を解析するソフト。ソフトの計算結果をDOE公表データと比較、精度を確認。
2.計算機上で、搭載する233ウラン燃料を削減、外部核融合中性子量を投入する量と場所を計算機上で最適化する。
共創で実現したいこと
A.小型核融合炉設計
1.重粒子重陽子加速器:医療用加速器メーカーの協力を求めます。
2.循環風洞設計試作:高圧水素ガス圧縮機が必須。ガス圧縮機メーカー、高圧ガス事業者、大学、研究所の参加を求めます。
3.共創で生じた、新たな知財は、項限度に応じて、当社と持ち分比率を決定する。
B.未臨界トリウム核分裂炉
1.核分裂炉心設計用シミュレーションコードの開発:実績のある米国DOEのShippingport Atomic Station の未臨界トリウム炉を計算機上に再現、核分裂反応と中性子拡散過程を解析するソフトの開発。ソフトの計算結果をDOE公表データと比較、精度を確認。
2.計算機上で、搭載する233ウラン燃料量をを削減、未臨界土を深める改造。外部核融合中性子量を投入する量と場所を計算機上で変化させ、外部中性子の入射位置と形状、入射量を最適化する。
3.共創で生じた、新たな知財は、項限度に応じて、当社と持ち分比率を決定する。
C. 当社は、共同研究、開発ネットワークの共創者対し、2025年度末に、Initial Design Package を交付する。
求めている条件
我々は、科学者、技術者集団であり、人知を求め、自由世界からの投資を歓迎する。
学界に対し、他分野との研究交流を願い、積極的に共同研究、研究分担を進める。。
経済界に対し、2025年度末までに、実用性、市場性が高い、ハイブリッド未臨界炉に関するInitial Design Package を発表する。
(ただし、当該Initial Design Packagr には、本件基礎デザイン活動に参加した、個人または法人等に係わる一切のの知財は秘匿され記載されない。これら知財の保護は、基本的に、日本の民放、会社法、特許法等関係法令にしたがうものとする。
当会社は、上記秘匿知財に抵触しないことを前提として、日本及び世界各国の政府及び各種VC 等の後部課題、資金提供に応じる用意がある。
2035年以降、当該中小型原子炉のマーケットは急拡大すると想定される。重工業、重電各社、電力会社の御協力を給わりたい。
こんな企業と出会いたい
ビジネス領域
- 画像・映像データ
オープンイノベーション実績
(内閣府)ImPACT プログラム:「核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化」 PM名: 藤田玲子
研究開発課題名:「核融合中性子のLLFPの分離・核変換への応用」
研究開発機関名: 学校法人中部大学 中部大学 研究開発責任者 佐藤元泰
科学研究費 新学術領域 「宇宙観測検出器と量子ビームの出会い。新たな応用への架け橋」
計画研究 B02「マッハ衝撃波干渉領域での飛行中ミュオン触媒核融合の創生」 研究代表 木野康志、副代表 佐藤元泰
特許 1.特願2022-028723、 2022/02/26出願 「発電システム及び発電方法」(内容:核融合駆動-トリウム未臨界炉)
2.特願2021-073711、 2021/04/25出願 「核融合システム、核融合方法、長寿命核分裂生成物の核種変換短寿命化処理
システム及び長寿命核分裂生成物の核種変換短寿命化処理方法」
3.特許7018222号 2021/11/01登録 「核融合システム、核融合方法」
論文 1.A. Iiyoshi, M. Sato, et.al.,.A Safer, Smaller, Cleaner Subcritical Thorium Fission - Muonic Fusion Hybrid Reactor,
Fusion Science and Technology, ANS (2023), ISSN: Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/ufst20
2. A. Iiyoshi, M. Sato, O. Motojima, et.al., Muon Catalyzed Fusion Present and Future”, Proceedings of the International
Conference on Advances and Applications in Plasma Physics (AAPP 2019) , AIP Conf. Proc. 2179, 020010-1–020010-7
企業情報
- 企業名
- (株)Fusion Fission Powers
- 事業内容
- 核融合で制御する小型の未臨界固体トリウムエネルギー源を考案、開発を始めたい。原理的に暴走しない、未来に放射化物を残さない。これを2030年までに実現。工場で組み上げ時に放射化物なし。現地搬入、組立後、核融合エネルギーをぞうふくし、エネルギーを生産。運転終了時には、長寿命核廃棄物が残らない。 廃熱による海水淡水化、農業用水生産、下水浄化等、発展途上のグローバルサウス諸国の人口110万人未満の中小都市インフラ設備を展開する。
- 所在地
- 京都市下京区四条通り室町函谷鉾町101リージャス四条烏丸センター6Fセンター
- 設立年
- 2023年
プランのアップグレードで企業情報をご確認頂けます
プラン詳細はこちら