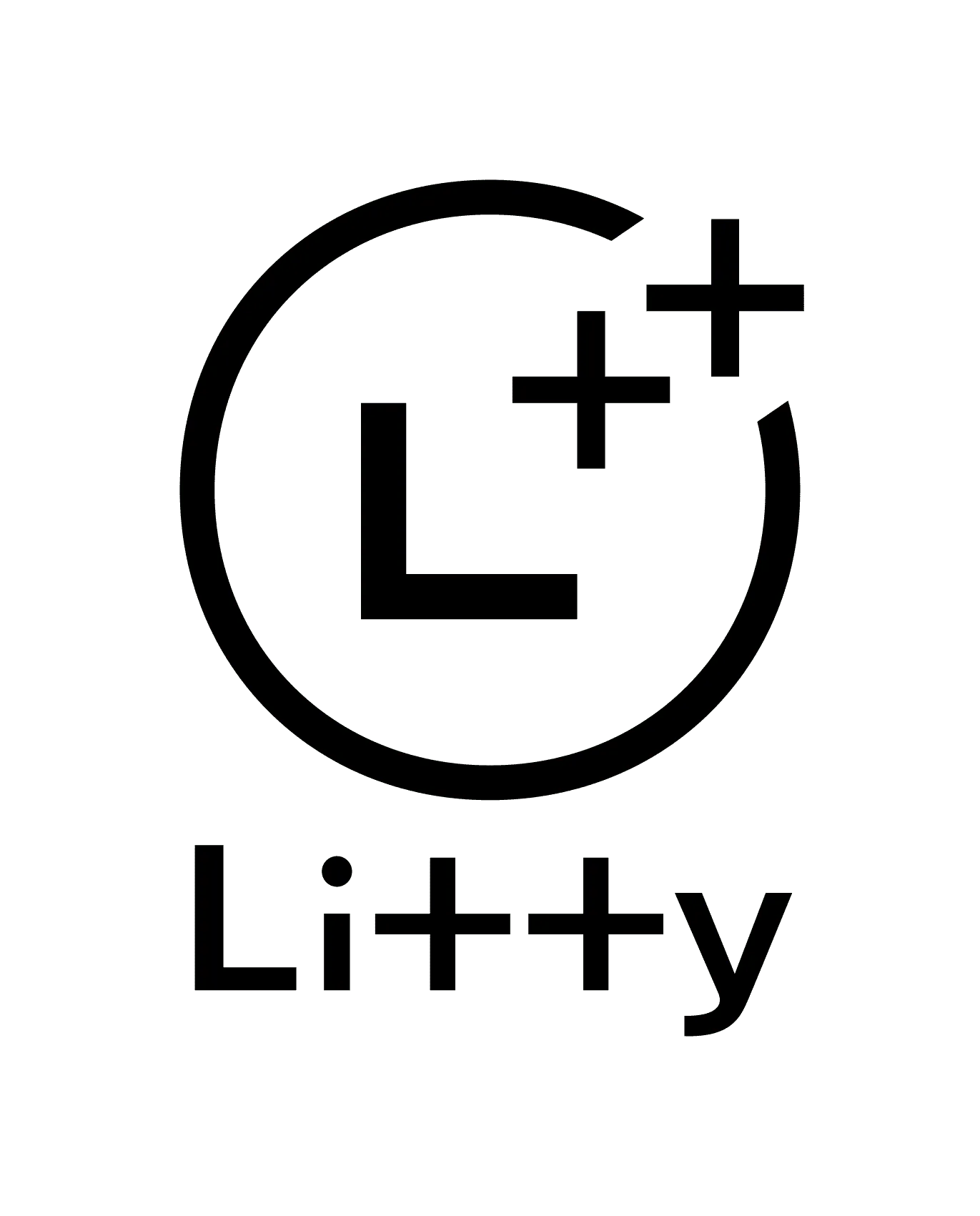- 公開:2025年11月10日
- 更新:2025年11月10日
東京都環境局が推進する「断熱窓改修」促進の共創プログラム始動!――業界のリーディングカンパニー3社(三協立山・LIXIL・YKK AP)がスタートアップと挑む
三協立山株式会社

- 非鉄金属
- 鉄鋼
- 加工
- 事業提携
- 中小企業
東京都環境局は、住宅分野の脱炭素化を推進するため、『断熱改修の新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム』を開始した。本プログラムは、スタートアップなどの技術・アイデアを取り入れながら、断熱改修を社会に広げる新たな仕組みづくりを目指すものだ。
今回、ホスト企業として参画したのは、三協立山、LIXIL、YKK APの3社。各社は、建材・窓など住宅分野における強みを活かし、既存住宅の断熱改修を促進する新サービスの創出をテーマに、スタートアップをはじめとしたパートナー企業を募集。共創を通じて、断熱改修市場の拡大と新たな価値の創出を目指す。一方、東京都環境局は、設定したテーマの実現に必要な実証等に充てる協定金として1プロジェクトあたり最大500万円を支給するほか、採択後の事業化に向けアクセラレーターを通じて伴走支援、広報・PR支援を実施する。
<ホスト企業3社と募集テーマ>(企業名50音順)
●三協立山株式会社
「開口部改修技術を活用した生活者の暮らしの価値向上と、現場労働力不足に悩まされない業界構造の転換」
●株式会社LIXIL
「世界的な気候変動に対応した“窓”“ドア”開口部の断熱改修の促進 未来の新たなスタンダードを創出」
●YKK AP株式会社
「QOLの常識を窓で変える ~リフォームの新しい仕組み作りへの挑戦~」
そこで今回TOMORUBAでは、主催者である東京都環境局と、ホスト企業3社の担当者に取材を実施。プログラムの狙いや背景にある社会課題、共創で実現したいこと、そして断熱改修の持つ可能性を掘り下げた。
【東京都環境局】 既存住宅の断熱改修で、脱炭素と暮らしの豊かさを追求する
――まず、今年度より『断熱改修の新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム』を開催することになった背景を教えてください。
東京都・小山氏 : 世界では、2050年に向けて温室効果ガスゼロを目指す取り組みが進んでいます。東京都でも、2030年までに2000年比で50%削減する『カーボンハーフ』を目標として掲げ、さまざまな施策に取り組んでいます。これらは環境局だけでなく、国や区市町村、企業、団体とも連携しながら展開中です。
今年3月には、新たな戦略『Beyond カーボンハーフ』を策定しました。2030年の目標だけでなく、その先を見据えた取り組みをどう進めていくかを示すものです。その中で重点プロジェクトのひとつとして『既存住宅断熱倍増プロジェクト』を立ち上げました。今回のアクセラレータープログラムは、本プロジェクトの推進施策の一環で開始しています。

▲東京都 環境局気候変動対策部 家庭エネルギー対策課長 小山利典氏
――既存住宅の改修数を倍増させる野心的なプロジェクトになりますが、断熱改修の課題は何でしょうか。
東京都・小山氏 : 従来からある課題は大きく2つで、コスト面と、断熱の効果やメリットが十分に浸透していないことです。この2点については、これまでも東京都として補助制度などを通じた支援を行ってきました。企業の皆さんにも助成制度の活用や情報発信を通じて、断熱のメリットを広く周知していただいています。
さらに、今回のプログラムに関連する課題としては、リフォーム事業者が断熱改修を進めやすい環境が整っていないことも挙げられます。これまで行政は助成金などの支援策を中心に取り組んできましたが、リフォーム事業者の多くは水回りなど得意な工事に偏る傾向がありました。
しかし、断熱改修、特に窓などの手軽にできる改修にもビジネスチャンスがあると感じてもらうことが、取り組みを一歩前進させる重要なポイントだと思います。今回のプログラムは、そうした環境整備を後押しするという点でも大きな意義があると思います。
――プログラムには、ホスト企業として3社(三協立山、LIXIL、YKK AP)が参加されます。ホスト企業には、このプログラムを通じてどのようなことを実現してほしいですか。
東京都・小山氏 : このプログラムでは、競合する企業も同じ場に入り、断熱効果の認知不足等消費者側の課題や人手不足等工務店の課題等、業界全体の課題解決にチャレンジします。スタートアップの技術等を活用した共創により課題解決の糸口の気づきも生まれるでしょう。もちろん、課題解決につなげていただくことが一番重要ですが、その先に「まだやれることがあるのではないか」「自分たちで新しい挑戦をしてみたい」と考え、次々とイノベーションを生み出してもらえると嬉しいです。
窓サッシメーカー業界は1社1社が非常に大きな企業であり、それぞれがイノベーションを起こし、市場を切り拓く力を持っています。このプログラムが、そうした変化を起こすきっかけになればと思います。
――本プログラムでは、実証等に充てる協定金として1プロジェクトあたり最大500万円を支給するなど、手厚い支援も特徴です。このほか、東京都のバックアップ体制についてもお聞かせください。
東京都・小山氏 : プログラムの運営会社としてeiiconさんに参画いただき、調整役として課題の抽出からプログラムの設計まで、一緒に進めていく体制を整えました。さらに、専用のWebサイトも立ち上げ、事業の広報や共同プロジェクトの成果、スタートアップを含めた各社の取り組みなどを発信していく予定です。東京都の名前も出しながら、情報発信面で力強く支援していく考えです。予算の範囲内で金銭面での支援も実施します。
――小山さんから見て、今回のプログラムの最大の特徴はどこにありますか。
東京都・小山氏 : これまで行政が行ってきたマッチングは、比較的近い業界同士をつなぐケースが多かったのですが、今回はスタートアップとの連携という点で、これまでにない特徴があります。行政だけではスタートアップを見つけるのは難しいのですが、今回はeiiconさんにコーディネートしていただくことで、異業種とのマッチングや連携の実現に大きな期待を持っています。

――このプログラムで達成したい目標は?
東京都・小山氏 : 短期的には、2026年3月までと期間は限られますが、一定の成果が出ることを期待しています。長期的には、ホスト企業に「スタートアップとの連携で新たな気づきを得られる」と感じてもらい、自社の中で改めて断熱の課題を認識したうえで、次につながるヒントを得ていただければと思います。そうした経験が、将来の新しい機会につながり、事業が発展していくことを願っています。
――最後に、応募を検討されているスタートアップの皆さんにもメッセージをお願いします。
東京都・小山氏 : GXやカーボンニュートラルの取り組みは、確実に世界的に広がっていきます。日本の脱炭素の施策に関して、特に都市部では建物のエネルギー消費を下げることが不可欠です。新築建物では規制や基準が整えられており、対策が進んでいる一方で、圧倒的に多いのは既存の建物であり、この分野にはまだまだ伸びしろや手法の余地があります。ぜひこの可能性に注目し、市場に飛び込み改革を起こすという気概を持って前向きに取り組んでほしいです。
また、断熱改修はどうしても気候変動という切り口で語られがちですが、本質的には快適な住まいを作ることにつながり、人々の生活の豊かさや快適性にも直結します。脱炭素の視点だけでなく、人々の幸せに結びつく取り組みだということを意識しながら、一緒にプログラムを進めていければと思っています。
【三協立山】 「開口部改修技術を活用した生活者の暮らしの価値向上と、現場労働力不足に悩まされない業界構造の転換」

――続いて、プログラムのホスト企業である三協立山さんにお伺いします。最初に、御社の事業概要と特徴を教えていただけますか。
三協立山・柿澤氏 : 三協立山は、住宅用建材やビル用建材などを開発・製造・販売している会社です。長期的に目指す方向として、サステナビリティビジョン2050『Life with Green Technology 〜「環境技術でひらく、持続可能で豊かな暮らし」を実現する企業グループへ~』を掲げており、その実現を目指しています。
2030年のカーボンハーフ、2050年のカーボンニュートラルに向け、私たち建材メーカーができることは何かと考えた際、やはり断熱商品を世の中に送り出し、広く普及させていくことだろうと考え、その取り組みを強化しているところです。

▲三協立山株式会社 執行役員 開発統括部長 柿澤秀則氏
――窓断熱市場の現状や御社の課題は?
三協立山・柿澤氏 : 断熱サッシ市場では、樹脂サッシの断熱性能が最も高く、次いでアルミ樹脂複合サッシが続きます。リノベーション向けには内窓の販促も活発です。かつては単板アルミサッシが主流でしたが、アルミのペアガラスサッシ、続いて樹脂サッシとアルミ樹脂複合サッシが登場し、シェアを伸ばしてきました。現在、当社が注力するアルミ樹脂複合サッシがトップシェアを占めますが、伸長する樹脂サッシへの対応が課題です。
業界全体を見ると、新築需要は人口減少とともに減り続けており、窓の出荷枚数も減っています。こうした状況の中、各社はリフォーム需要に注目し、商品価値を高めて潜在需要を掘り起こそうとしています。当社としても新築だけではなく、リフォーム市場への進出を加速させていく考えです。
――今回のプログラムへの参加を決めた理由もお伺いしたいです。
三協立山・柿澤氏 : 東京都の掲げる趣旨に賛同したことが参加の理由です。先ほど申し上げたように、当社はリフォーム事業を強化していこうとしているため、東京都も同様に断熱改修の重要性を考えていらっしゃるのであれば、私たちにとっては絶好のチャンス。エンドユーザーに断熱サッシや建材のことを知っていただく良い機会になると考え、このプログラムへの参加を決めました。
――今回の共創プログラムを通じて、どんなことを実現したいとお考えですか。
三協立山・小林氏 : 実現したいことは大きく2つあります。1つ目は、生活者の暮らしの価値向上です。窓を改修することで、気密性や遮音性といった性能を高めることができます。さらに、近年増えている犯罪や異常気象への備えとして、防犯・防災機能も付加したいと考えています。こうした機能の追加により、より安心で快適な暮らしに貢献することを目指します。このテーマでは、独創的な防犯・防災のアイデアを持つ企業とともに、新しい製品を生み出していきたいです。
2つ目は、生産労働人口の減少と施工現場の高齢化への対応です。例えば、現地調査の際に窓の採寸を行う流れになっていますが、この業務を担う担当者が不足しています。そこで、現在は人の手を介して行っている採寸などの業務を、何らかの技術を使って自動化できればと思っています。
加えて、サッシの取り付け作業も複雑で時間がかかりますし、取り付けを行う職人さんも足りていません。受注機会を逃すこともあるため、改善したいと思っています。例えば、施工時間を短縮できる新しい方法のアイデアや、ビスで行っている固定を別の方法で快適に行えるようなアイデアなどをお持ちの企業を求めています。

▲三協立山株式会社 開発統括部 商品開発二部 部長 小林光裕氏
三協立山・横本氏 : 自分たちとは違った目線や切り口を持つ企業さんとマッチングできれば、新しいものが生まれるのではないかと思っています。そんな可能性に期待しています。

▲三協立山株式会社 渉外調査部 兼 ビル統括部 統括部長付(東京駐在)横本吉永氏
――御社と協業するメリットについてもお伺いしたいです。
三協立山・小林氏 : 改修に関する商品や工事ノウハウは提供可能です。30年〜40年前に作られた窓の図面情報も社内に揃っており、パートナー企業の方にデータを共有したり、即座にLINEで読み込んだりといった活用もできます。また、サッシは品質精度が重要ですが、当社にはその確認ができる試験装置もあります。加えて、販売会社や施工担当チームもグループ内にあり、ノウハウや情報を開示できるほか、パートナー企業のアイデアを実証するフィールドとしても活用いただけます。
――最後に、応募を検討しているパートナー企業に向けてメッセージをお願いします。
三協立山・柿澤氏 : 建材業界に下地がなくても、まずは私たちの取り組みに興味を持ち、深く理解していただきたいと思います。そして、取り組みを始めたら諦めず、少しでも成果を出していければと考えています。
三協立山・横本氏 : 建材を違った目で見ていただき、新たなものができればすごく面白いと思います。それが実用化され、特許取得につながれば大きな成果です。ぜひ、長期的な協業を目指して取り組んでいければと思います。
三協立山・小林氏 : 社内で新しい技術などを探す際には、どうしても時間がかかることがありますし、意思決定がなかなか進まないこともあります。その点、今回のプログラムは、迅速な判断のもとで進められると考えています。カーボンニュートラル促進に向け、既存住宅の断熱改修は必要不可欠です。この分野で共創していただける企業の皆さまには、ぜひ積極的にご応募いただきたいです。
【LIXIL】 「世界的な気候変動に対応した“窓”“ドア”開口部の断熱改修の促進 未来の新たなスタンダードを創出」

――まずは、御社の目指す方向性や断熱関連事業の特徴についてお聞かせください。
LIXIL・渋谷氏 : LIXIL全体では、現社長のもとで『インパクト戦略』を打ち出し、世界的な社会課題への対応に取り組んでいます。特に優先するテーマが『グローバルな衛生課題の解決』『水の保全と環境保護』『多様性の尊重』の3つで、今回のプログラムは、このうち環境保護に関わるものとなります。
環境保護の取り組みでは、国もGX(グリーントランスフォーメーション)のロードマップを策定し、カーボンニュートラルや脱炭素を進めています。その中で重要な施策のひとつが断熱です。新築住宅はZEH(※)基準の義務化が進み断熱性能は高まっていますが、既存住宅の多くはまだ改善の余地があります。
特に昔の家だとガラス一枚の窓が多く、窓があってもほぼ外気と室内が同じ状態。そこで今回のプログラムでは、特に窓という開口部に焦点を当て、断熱普及を通じた環境保護の実現を目指したいと考えています。
※ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス):断熱性能の向上や省エネ設備、太陽光発電の導入により年間のエネルギー収支を実質ゼロ以下にすることを目指した住宅。

▲株式会社LIXIL HOUSING TECHNOLOGY 営業本部 リフォーム推進部 部長 渋谷和徳氏
――窓の断熱改修分野で、特に売れている御社の商品は何ですか。
LIXIL・渋谷氏 : 最も売れているのは内窓(インプラス)ですね。窓の改修には「内窓」「カバー工法」「はつり工法」の3つの工法があります。内窓は既存の窓の内側に窓を追加する方法で、カバー工法は、既存の窓枠の上から新しい窓を取り付ける工法。はつり工法は、壁を切って新しい窓を入れる方法です。内窓は、既存の窓を触らなくてもいいので1時間ほどの工事で済み、手軽に断熱性能を高められる点が選ばれる要因となっています。
――今回、『断熱改修の新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム』にホスト企業として参画を決めた理由は?
LIXIL・今村氏 : 長年、当社では断熱の重要性を世の中に広めようと活動を続けてきましたが、いまだ一定の壁を越えられないという課題感があります。これまで調査結果を発信したり、さまざまな商品を展開したりしてきましたが、断熱の価値が十分に伝わっていないのが現状です。そこでこのプログラムでは、私たちの中にある既成概念を打ち破るようなスタートアップと出会い、新たなブレイクスルーを生み出せればと考え、参画を決めました。

▲株式会社LIXIL Design & Brand Japan ブランド & マーケティング ストラテジー プロダクトマーケティング部 第1グループ 今村誠太郎氏
――具体的には、どのようなことに取り組んでいきたいですか。
LIXIL・丸田氏 : 1つ目は、需要を掘り起こすための仕組み作りです。断熱リフォームを行うと、「冬の寒さがやわらいだ」「光熱費が下がった」「結露がなくなった」といった声を多くいただきます。リフォームされた方の中には「他の部屋もやってみよう」とリピートしてくださるケースも少なくありません。こうした体験者の声は、どんな広告よりも説得力があります。そこで、この喜びの声を多くの人に波及させるプラットフォームを構築し、断熱リフォームの素晴らしさをさらに広げていきたいと思っています。
2つ目が、見えない価値の可視化です。断熱の効果は見えないものなので、どう自分事に変換させるかが課題です。現状では「あなたの家の断熱は、これだけ節電効果があります」といった伝え方はしていますが、これ以外にも、スタートアップの革新的なアイデアから、まったく新しいコミュニケーション手法を生み出せないかと考えています。
3つ目は、潜在層に向けた住まいへの関心向上と行動誘発の仕組み作り。暮らしの中の見えない不快感に気づかず我慢している人は多く、例えば、1枚ガラスの窓辺では冷気が流れ込み非常に寒いのですが、解決策を知らない人から見れば、寒さが当たり前になっています。こうした点を、広く伝えるアイデアを募集したいです。

▲株式会社LIXIL 渉外部 事業渉外グループ 係長 丸田優士氏
――共創の実現に向け、御社から提供できるリソースは?
LIXIL・渋谷氏 : 全国に約1万1,000社の工務店やリフォーム会社のネットワークを持っており、これは業界最大規模です。このネットワークを通じて、窓の断熱に関する教育やツールの提供も行っています。今後、本プログラムでトライアルを実施する際には、このネットワークを活用することが可能です。
LIXIL・丸田氏 : また、窓に関する知見も豊富です。LIXILに統合する前にトステムという会社があったのですが、トステムに関して言えば、100年近く窓というものに真剣に向き合って技術開発を行ってきました。そのため、開口部に対する困り事のソリューションはたくさん持っています。窓に限らず断熱材など家全体の断熱に関する研究も行っており、データも潤沢に保有。そうした点が当社の強みだと思います。
――応募を検討している企業に向けてメッセージをお願いします。
LIXIL・丸田氏 : 私たちは断熱に真剣に取り組むメーカーだと自負しています。ただ、社内だけで議論していると、どうしても考えが凝り固まりがちです。今回のプログラムでは、私たちが見落としがちな視点にも注目して、柔軟に提案してくれるパートナーと一緒に共創できればと思っています。
LIXIL・今村氏 : 2050年のカーボンニュートラルや東京都のゼロエミッションを目指す中で、家庭部門のCO2削減は避けて通れません。しかし、既存住宅の断熱改修はまだ十分に進んでおらず、大きな市場が残っています。この市場を一緒に大きくしていける、高い志を持つパートナー企業と共創していきたいです。
LIXIL・渋谷氏 : 住宅性能は耐震性と断熱性で判断されます。耐震性は命に関わるため改修されやすい一方で、断熱は冬のヒートショックや夏の熱中症など健康に影響するにも関わらず、重要性があまり知られていません。
そのような点を伝え、約5,000万人が暮らす既存住宅の性能を高めていきたい。高性能な新築と既存住宅のギャップを改善する活動にしたいと思っています。この問題に対し、トライアンドエラーを重ねながら、前向きにチャレンジしていけるパートナーと一緒に取り組みたいです。
【YKK AP】 「QOLの常識を窓で変える ~リフォームの新しい仕組み作りへの挑戦~」

――はじめに、御社の事業概要や特徴からお聞きしたいです。
YKK AP・筒井氏 : YKK APは、住宅の窓やドア、ビル用建材(カーテンウォールなど)、エクステリア商品などの製造・販売を行う建材メーカーです。母体は1934年に吉田忠雄が創業したサンエス商会で、ファスナーの加工販売からスタートし、現在はファスニング事業を担うYKKへと成長しています。YKK APは、YKKグループの中で建材事業を担い、1957年設立、1959年にアルミの溶解や押出の操業を開始し、1961年にアルミ建材の製造・販売を開始、2002年に現在の社名になりました。
YKKとYKK APを中心としたYKKグループは「善の巡環」という精神を事業活動の基本とし、品質にこだわるモノづくりを大切にしています。その象徴が一貫生産体制です。窓やドアといった主力製品はもちろん、ネジなどの部品や、それらを作る機械までも自社で製造。この体制が高い品質を支える基盤であり、創業以来守り続けています。当グループは、こうしたモノづくりを通じて世界70カ国/地域で事業を展開しています。

▲YKK AP株式会社 住宅・エクステリア統括本部 首都圏統括支社 東京支社長 筒井康輔氏
――断熱関連の事業については、どのような特徴がありますか。
YKK AP・筒井氏 : 当社は早くから高断熱住宅に注目し、2009年に樹脂窓APWシリーズの製造・販売を開始。もともと寒冷地向けだった高断熱窓を全国展開するため、製造ラインや商品群を整備し、日本の高断熱窓の普及の一翼を担ってきました。新築だけでなくリフォーム向け商品も展開しており、1985年発売の内窓『プラマードU』は40年以上のロングセラー。2025年にはマンションリフォームへの対応力向上も図ったリフォーム用樹脂窓の新商品『ウチリモ 内窓』も発売しています。
2021年には、既存住宅の断熱と耐震の性能向上を目的に『性能向上リノベの会』を立ち上げました。既存住宅の診断や改修は専門知識が必要で敬遠されがちです。そこで私たちは、営業・技術の両面からサポートしています。現在は、全国で650社超の工務店やリフォーム会社、設計事務所などが参加し、断熱リフォームを中心に住宅性能を底上げする取り組みを進めています。
――このプログラムにホスト企業として参画を決めた理由は?
YKK AP・小沼氏 : 当社は新築・リフォームの両軸で高断熱商品の製造・販売を続けてきましたが、既存住宅の断熱改修はまだ道半ばです。進まない理由はいくつかありますが、特に改修によるメリットがエンドユーザーに十分伝わっていないことが大きな要因です。そこで、プロモーションや仕組み作りの面で他社の力を借り、この課題を打破していきたいと考え、今回の取り組みに参画しました。

▲YKK AP株式会社 住宅・エクステリア統括本部 首都圏統括支社 東京支社 リノベーション営業推進部 課長 小沼希実氏
――具体的に、どのような共創を実現したいとお考えですか。
YKK AP・小沼氏 : 掲げたキャッチコピーが『QOLの常識を窓で変える』です。脱炭素や省エネといった社会課題はよく耳にしますが、多くのエンドユーザーには自分事として捉えられておらず、関心が低いことが問題だと捉えています。そこで、私たちは健康と断熱の関係にフォーカスすることにしました。
実は、家の中で最も熱の出入りが多いのは「窓」です。夏は室内に入る熱の約7割、冬は外へ逃げる熱の約5割が窓からといわれています。どんなに壁や屋根の断熱材を良くしても、窓が古いアルミ製の1枚ガラスでは、いわば“穴の開いたバケツ”のような状態なのです。日本の既存住宅の約7割はいまだにこのタイプの窓で構成されており、断熱性能の向上が大きな課題となっています。
当社では、品川に窓の断熱性能を体感できるショールームを設け、これまでプロユーザーの方々に断熱の大切さを伝えてきました。しかし、一般の方々にはまだ十分に伝えきれていません。今回のプログラムではパートナー企業と、断熱に関心のないエンドユーザーにも働きかけ、暮らしの快適さや健康との関係をよりわかりやすく伝えるアプローチ方法を模索したいと思っています。
――どのようなパートナーと共創を実現していきたいですか。
YKK AP・小沼氏 : 私たちは商品力には自信がありますが、エンドユーザーへのアプローチや仕組み作りには苦手意識があります。そこで、テクノロジーを活用して断熱の価値を一気に広められるパートナーを求めています。
具体的には、ヘルステックを実現する生体センシングや行動検知といった技術です。健康と住環境の関係に関するデータは揃っているものの、エンドユーザーに響く形で発信できていません。持っているデータを新しい方法で活かし、今までにないユーザー体験を提供できるパートナーを期待しています。
また、今回は賃貸住宅向けの共創イメージも掲げましたので、フィンテックや不動産テックの領域のパートナーにも期待しています。
――御社と協業するメリットについてもお伺いしたいです。
YKK AP・小沼氏 : 内窓の製造・販売を40年以上続けてきた経験があり、そこで築いた信頼と実績が強みのひとつです。また、商品開発と並行して住空間に関する技術解析も行っており、窓の開き方による通風量や音の軽減効果などを見える化しています。品川のショールームには全身で体感できる装置もあり、こうしたデータや施設を共創の場として活用することも可能です。
さらに、SNSでの豊富なコンテンツを保有しています。YouTubeのほか、Instagram、X、Facebookなどを運用しており、総フォロワー数は約23万人(2025年11月5日現在)。YouTubeでは社員の“ずーしみ”がYouTuberとして活動しており、動画コンテンツも充実しているため、こうしたSNS媒体やコンテンツも共創に活用できると思います。

▲ショールームには、断熱窓の性能を体感できる設備が整っている。(上写真は「ショールーム新宿」)
――最後に、応募を検討しているパートナー企業に向けてメッセージをお願いします。
YKK AP・小沼氏 : 私たちがともに実現したいのは、暮らしの心地よさを見える化し、QOLの新たな価値観を再定義することです。最近はタイパやコスパなど効率が重視されがちですが、本当の豊かさを一緒に追求していきたいと考えています。
YKK AP・筒井氏 : 今回の取り組みは、社会課題の解決を目指すものです。日本では既存住宅の断熱性能の低さが大きな課題となっており、その解決に向けてともに歩めるパートナーと出会いたいです。単に商品を売るのではなく、未来の子どもたちのために、新しい発想や知見を持つ方々と私たちモノづくりメーカーの力を合わせ、日本のために取り組んでいければと思います。
取材後記
新築住宅の断熱性能は向上しているものの、既存住宅は十分に対応されていない。このギャップを埋めるために、窓の断熱に特化したオープンイノベーションプログラムが立ち上がった。三協立山、LIXIL、YKK APという業界を牽引する3社がホスト企業として参加している点も非常にユニークである。取材をを通じて4者の意見を聞く中で、筆者も改めて窓断熱の重要性を実感した。今後、この取り組みが既存住宅の快適性向上や省エネルギー促進にどのような影響をもたらすのか、注目したい。
※『断熱改修の新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム』の詳細はこちらをご覧ください。
(編集:眞田幸剛、文:林和歌子、撮影:齊木恵太)