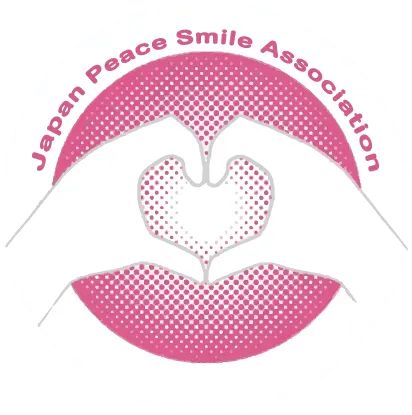- 更新:2025年11月07日
- 返信率:100%
ARTRIP(エビデンスのあるアートの対話鑑賞)で認知症予防と周辺症状を緩和し、世代間交流ができる共生社会を一緒に構築するパートナーを求めています。
一般社団法人Arts Alive

- 少子高齢化
- 地域活性化
- ハンドメイド
- 事業提携
- ジョイントベンチャー設立
- ラボ設立
- プロジェクト・イベント型(期間限定)での協業
- ネットワーキング
- 教育研究機関
- NPO・NGO
プロジェクトメンバー
責任者
プランのアップグレードで企業責任者情報を確認いただけます
プラン詳細はこちら
自社特徴
提供リソース
① 過去10年以上、認知症を含む高齢者を対象にアート創作、アートの対話プログラムを実施してきた実績、
② アート創作やアート対話が高齢者の心身の健康やうつ更に認知症の周辺症状BPSDや認知症予防に与える効果の検証を国際治験を含めて3回実施しています。検証に関しての知見があります。
③ この分野における国際的なネットワークがあり、将来的に開発されるデバイスを海外に紹介することが可能です。 健康度や幸福度を測るデバイスは、自宅でも美術館等でも使用することが可能です。
④ 代表の林は、国際博物館会議、および全国美術館会議の会員であり、国内、国際的に 成果を発表することができ、業界にインパクトを与えることができます。
⑤ 対認知症、高齢者の優れたファシリテーション力を持つプログラムのファシリテーターがすでに70名以上全国にいます。
⑥ 代表の林は、米国、ケースウエスタンリザーブ大学で、認知症とアートの研究をしており、共同研究者のDr. Peter Whitehouseや、モントリオール大学のDr. Oliveir Bouchetなど 認知症、認知症予防とアートの領域の第一人者と共同研究をしており、海外の研究者の協力を得ることが可能。代表は、海外の医学雑誌への論文投稿もあるアートの健康に与える効果の研究者である。 ⑦ 全国の美術館、高齢者施設、北区社会福祉業議会との連携実績など、パイロット事業に参加、協力してくれる高齢者がいる。
解決したい課題
① プログラムが心身の効果に与える影響を、映像撮影、解析するデバイスの開発 プログラム参加者の声や表情を撮影し、それを自動的に解析し、参加者がプログラムに参加する度に自らの参加を振り返り、評価することができるようなシステムを開発したい。 少しづつでも効果が表示されることで継続のモチベーションになる。 認知症の予防につながるプログラムはいずれも、長期にわたって定期的に参加することが重要なので、プログラムの楽しみとともに、効果がわかることはモチベーションになるし、また、認知力の低下が示されれば、それは早期な発見につながり、対応をすることができようになる。
② 海外が作成したウェルビーイング指標でなく、日本人にも適応する指標の構築 現在、世界で最も使用されてるウェルビーイング指標は、欧米人の幸福感を元にしているので、必ずしも日本の高齢者の幸福感を図るには適当でない。日本ならではの指標を構築し、それを元に効果を測定するデバイスが必要である。
③ インターネットの使用ができない高齢者が自宅で参加することができる映像と音声のインタラクティブなディバイスの開発。 例えば、高齢者が見ているTVを通して双方向のプログラムに参加できたり、他の方法でTVのスイッチをオンにするような簡便さで参加できるリアルタイム、双方向オンラインデバイスの開発と普及
共創で実現したいこと
① 全国の美術館や施設で独自アートプログラムを通して、認知症を含む高齢者のQOLとウェルビーイングを高めること
② 将来は、これらの非薬物療法が薬に代わる社会処方として認められるようにする
③ アートプログラムを通して、障害の有無に限らず孤独、孤立のない、共生社会を創出
④ そのためアートの心身の健康に対する効果をより説得力のある形で実証する。 アートの効果を測定できるデバイスの開発。
⑤ 参加型アートによる認知症予防、進行抑制と周辺症状(BPSD)の緩和
⑥ 障害や病気の有無にかかわらず、誰もがその人らしくありのままに生きることができる社会を構築する。
求めている条件
こんな企業と出会いたい
ビジネス領域
- 地方創生
- 検知技術
- 少子高齢化
- 地域活性化
- フレイル予防
- メンタルヘルス
企業情報
- 企業名
- 一般社団法人Arts Alive
- 事業内容
- アートの創造性と非日常性を用いてあらゆる人が最後の瞬間までその人らしく生きることができる共生社会をきづくことを目的に、①アート対話型鑑賞ARTRIPの企画、実施、②ACP(アートを用いた企業研修)③ ARTRIPの為のファシリテーター養成事業 ④ アートと高齢化に関する研究、調査 ⑤ フォトストーリー 写真を用いた物語創作事業
- 所在地
- 設立年
- 2009年
プランのアップグレードで企業情報をご確認頂けます
プラン詳細はこちら