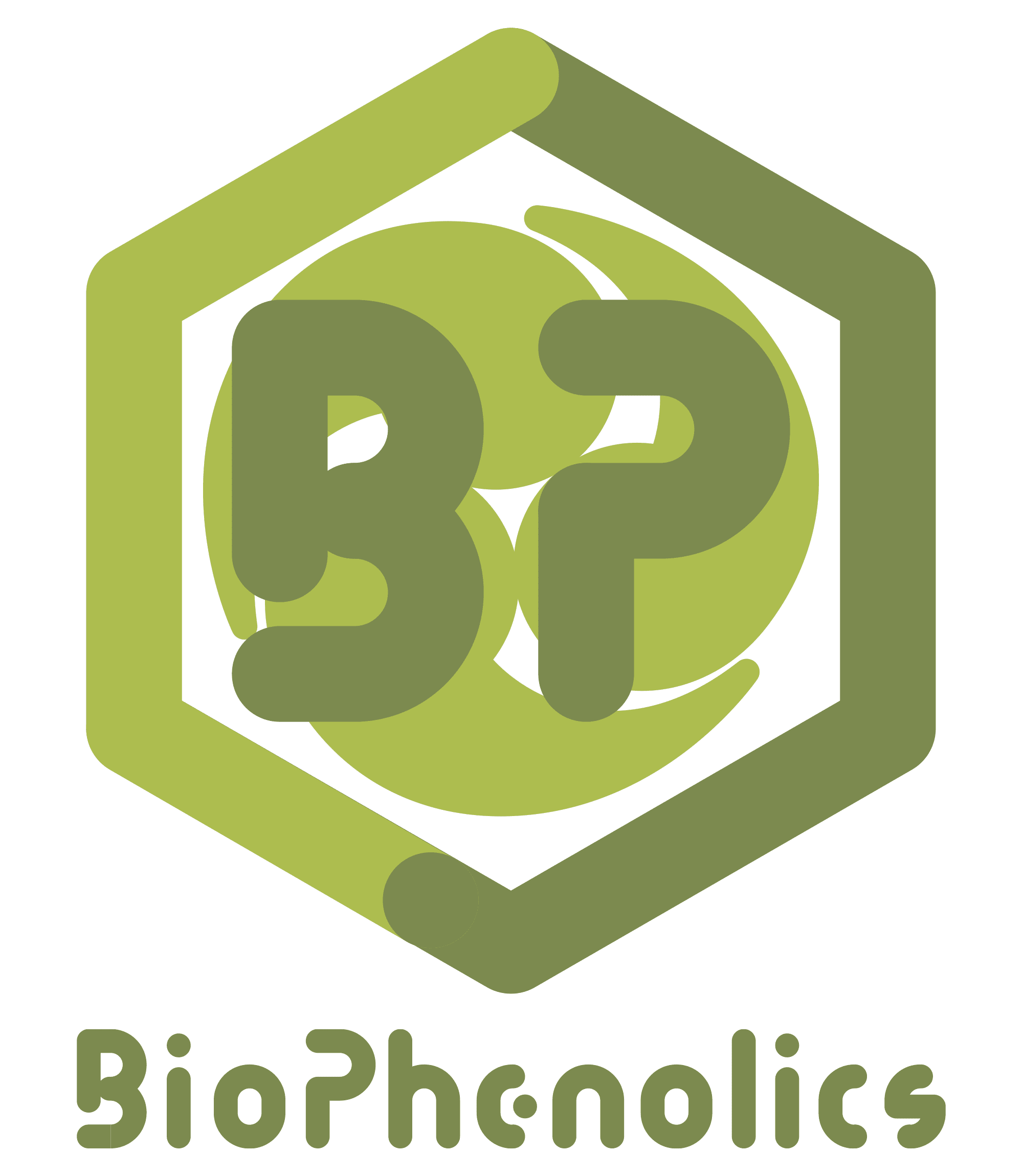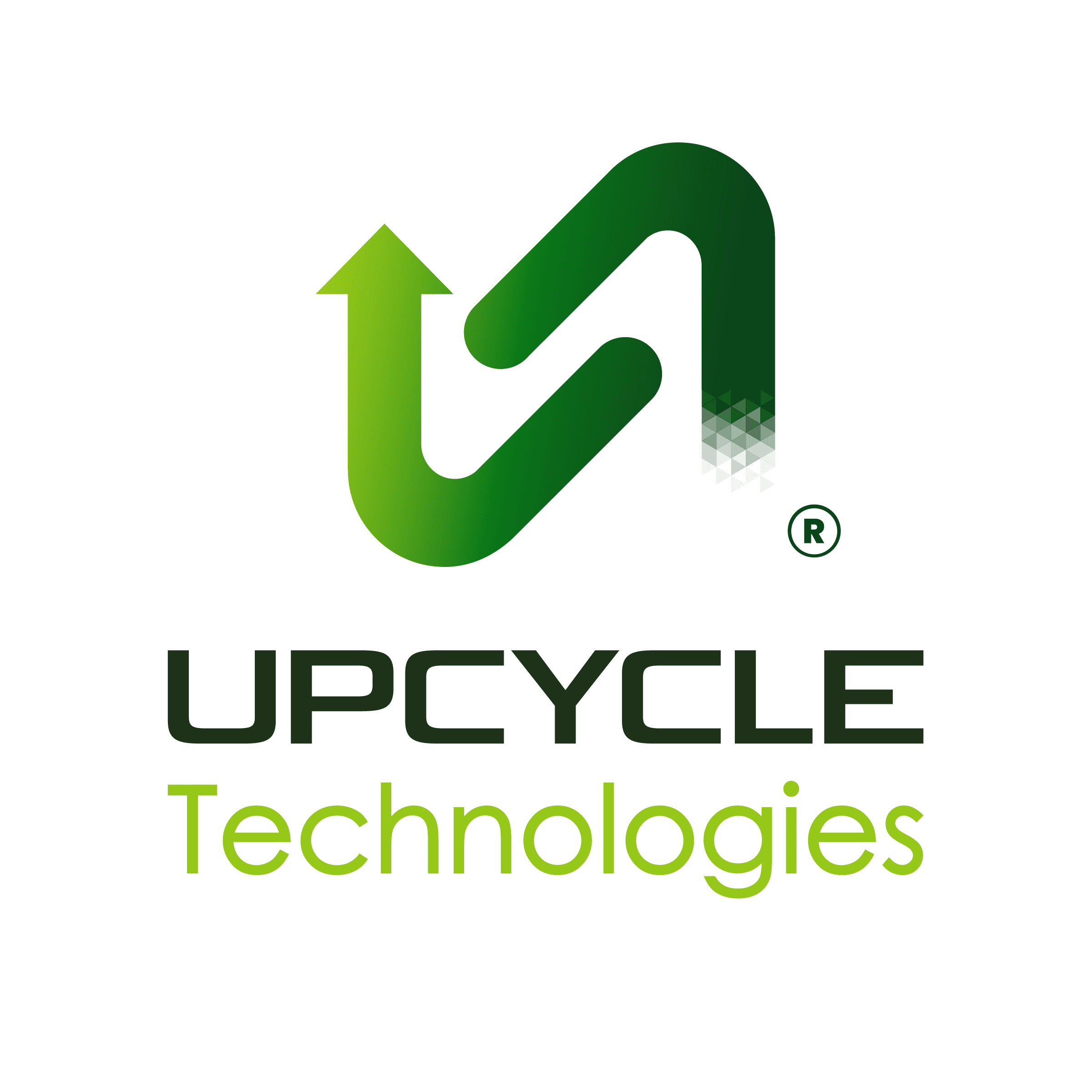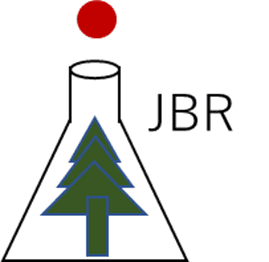- 更新:2025年03月03日
既存の石油合成原料に代わり、当社木質バイオマス新素材の活用による製品開発、実証、市場導入の共創。
PriMateria
- グリーン・サステイナブルケミストリー
- 事業提携
- ラボ設立
- 資金調達したい
- 新市場の模索
- 大学発ベンチャー
- 3カ月以内の提携希望
- スタートアップ
- テストマーケティング
プロジェクトメンバー
責任者
プランのアップグレードで企業責任者情報を確認いただけます
プラン詳細はこちら
自社特徴
「木質、植物などの自然有機物(バイオマス)を液化する技術」による石油代替の合成成分の研究、開発、製造
提供リソース
木質やコメ、麦、でんぷん、果糖、リグニン、セルロース、ヘミセルロースなどのあらゆる自然有機物(バイオマス)を化学的に分解、液化して環境に優しい、持続、再生可能な石油化学合成素材に代わる新たなバイオマス素材を生成する独自に創り出した化学的液化製法をコア技術として、国際社会が求めるエコフレンドリーで、カーボンニュートラルはもちろん、国際市場が求める安全性(ホルムアルデヒドフリー、BPAフリー)や産業界が求める既存の石油合成製品と同等以上の耐熱性、強度、軽量、耐薬品性などの機能性を持ち、成形加工しやすい素材を提供。
•CO2最大100%削減可能
•石油化学製品最大100%削減可能
•品質劣化せず、再生使用可能
解決したい課題
日本国内で流通しているバイオマスプラスチックの多くは木材、竹、コメ、麦、トウモロコシや植物、食品、紙パルプ等の廃材や鉱物を粉末にしたまま、異物等除去など精製プロセスや化学的な処理をしないまま、石油合成原料と混ぜ合わせた複合バイオマスプラスチックが一般的である。
そのため、品質が安定せず、高単価で、耐熱性、強度などの機械特性や成型性は石油合成代替製品として活用するのは容易ではない。
当社独自の木質バイオマス液化技術によるバイオポリエステル、レーヨン、ポリウレタン、フェノール樹脂等の木質由来合成製品を従来の石油由来と同等の価格、耐熱性、強度等の機械特性、成型性が高く、石油合成製品よりも非常に環境負荷が低い環境素材を提供いたします。
共創で実現したいこと
当社は「石油プラスチックに代わる、環境に優しい木材その他の植物由来の天然素材でプラスチックの世界を変える。石油プラスチックを使い続けることの課題を解決し、脱炭素社会の実現に貢献する。」というビジョンを掲げております。
それらを実現するために、共に手を取り合い、一緒に実現していただける協業先様を求めております。
求めている条件
パッケージング、自動車、航空機、食品・飲料、テキスタイル・ファッション等のメーカー様、建築、建設会社様で、リソースの活用や共同開発、新規事業立ち上げをご検討いただける会社様
企業情報
- 企業名
- PriMateria
- 事業内容
- 間伐材、廃材など木質の利用による新素材開発や石油プラスチックに代わる非可食の木質、植物由来、天然由来の複合樹脂素材の開発。
- 所在地
- 設立年
- 2024年
プランのアップグレードで企業情報をご確認頂けます
プラン詳細はこちら