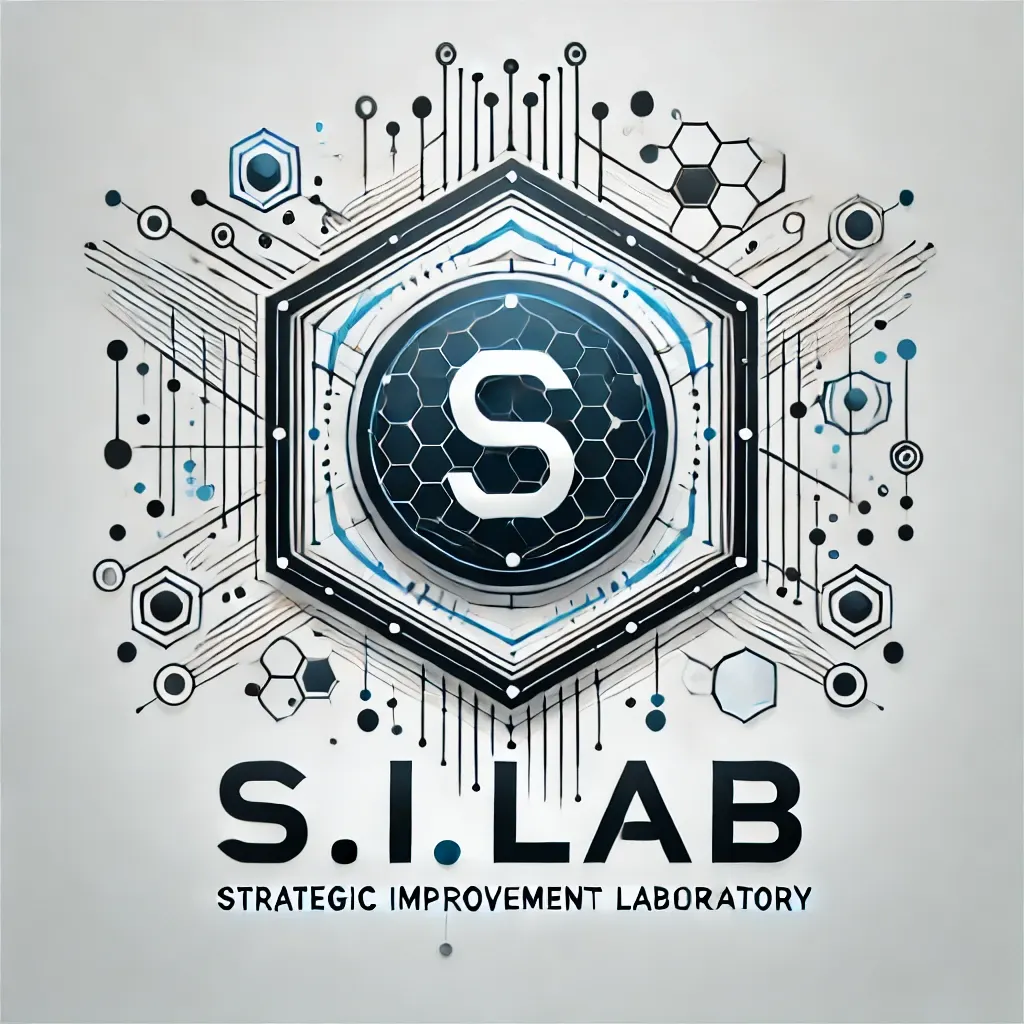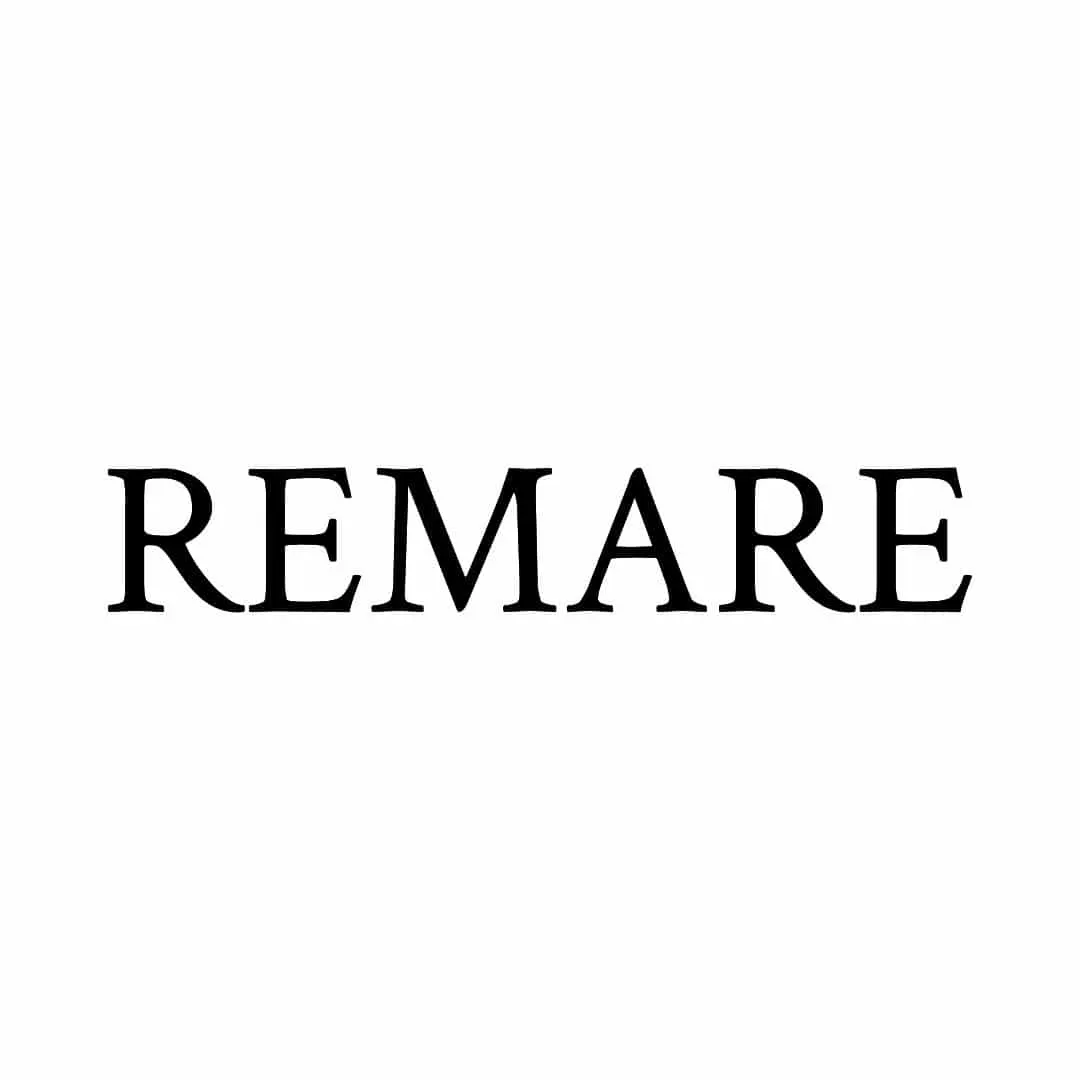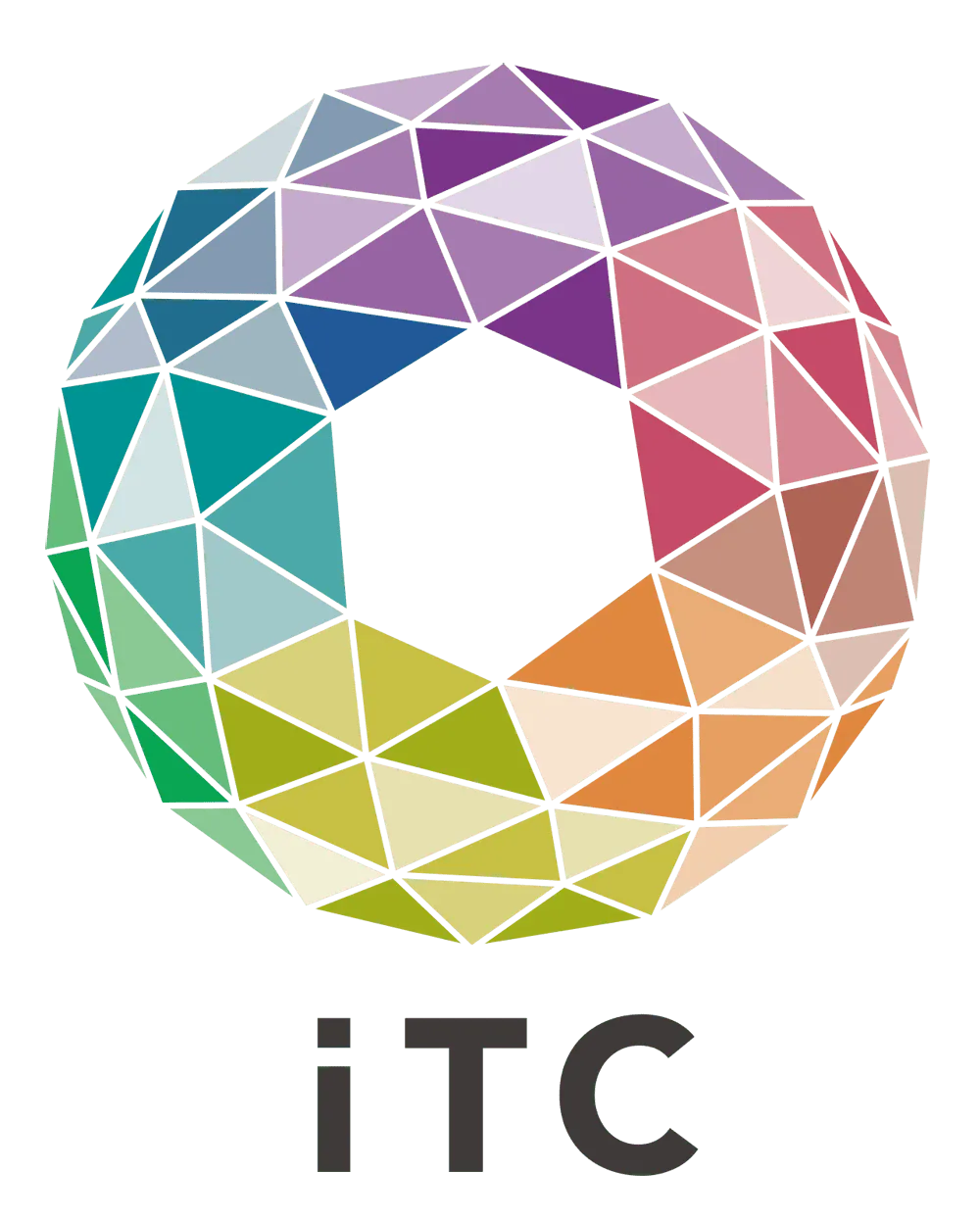- 更新:2025年10月28日
株式会社グリーンソリューション
- 環境問題
- リソース提供(既存技術の提供・特許流用の検討など)
- スタートアップ
プロジェクトメンバー

自社特徴
当社の最大の強みは、韓国PROPAC社との正式な契約に基づき、同社が開発した堆肥化可能な生分解性プラスチックの特許技術の譲渡を受けており、日本国内での特許出願を予定している点です。これにより、日本市場において当該素材を独占的に展開できる立場を確保しており、事業上の差別化優位を実現しています。 この素材は、従来のPLAやPBATと比較して、耐水性・耐油性・加工性・コスト面での総合性能が高く、食品包装用途での実用化に極めて適しています。また、素材単体ではなく、堆肥化装置とのセット提案や、今後開発予定の環境トレーサビリティ機能を含めることで、「脱プラ+廃棄処理+CO₂可視化」を一体的に提供できる統合型ソリューションを構築しています。 さらに、大手流通・包装資材企業とのPoCも進行しており、実行力と市場適合性を兼ね備えた事業展開が可能な点も当社の大きな強みです。
提供リソース
当社が提供できる最大のリソースは、単なる素材ではなく、環境対応を本質的に実現する「仕組み」そのものです。共創先にとって有益な点は以下の通りです: 国内独占展開権を持つ高性能な堆肥化対応素材 耐水・耐油・成形性・紙との複合化など、食品包装に必要な機能を備えた上で、国内に流通している他の生分解性素材と比べても、コスト面で導入しやすい価格帯を実現しています。脱プラの取り組みを「続けられるコスト」で始められる点が大きな利点です。 堆肥化装置と連携した循環モデルの提案 使用後の容器を食品残渣と一緒に堆肥化できる仕組みを構築することで、導入先の廃棄物処理コスト削減やESG効果を両立できます。 今後開発予定の環境トレーサビリティ機能 CO₂削減量やLCA指標を可視化できる仕組みを構築し、ESG開示や消費者への説明責任に貢献します。 柔軟でスピード感のある共創姿勢 共創先の要望に対して、スピーディに検証・実装できる体制を整えており、大企業では進めにくい新領域にも対応可能です。 これらのリソースにより、共創パートナーが「実行可能なコストで、意味のある環境施策を導入し、外部への価値発信ができる」ことを現場レベルから支援できるのが、当社の最大の強みです。
解決したい課題
当社は、環境対応型素材の技術的・価格的優位性と製品展開の構想を持っていますが、社会実装を加速するには、信頼ある大手企業との共創によって「実証フィールド」「市場浸透力」「スケール展開の体制」を確保することが不可欠です。 具体的には、素材の導入先となる食品製造ラインでの実証環境の確保、包装設計に関する実用試験・検証データの取得、さらには容器のライフサイクル全体(素材→廃棄→堆肥化→CO₂削減)の価値を社会に“見える化”して発信する力は、自社単独では限界があります。 こうした課題を、製造・物流・環境広報など多面的なリソースを持つ企業と連携し、部門横断的な共創PoCによって一歩ずつ乗り越えていくことが、事業の本格展開に不可欠だと考えています。
共創で実現したいこと
私たちグリーンソリューション株式会社は、脱プラスチックの社会的潮流の中で、環境負荷を根本から減らせる“真の代替素材”と、それを現実に普及させるための仕組みを提供することを目標としています。 現在は、韓国PROPAC社の堆肥化対応生分解性プラスチックに関する特許技術の譲渡を受け、日本国内での製品化・供給体制を確立することが最優先の目標です。加えて、素材の供給にとどまらず、堆肥化装置や環境トレーサビリティの仕組みと連携した循環型プラットフォームの構築を通じて、素材・廃棄・情報を一体化した社会実装モデルを生み出すことを目指しています。 私個人としては、単なる素材ビジネスに終わらせるのではなく、企業や自治体、そして生活者が“環境対応に参加できる仕組み”を築くことが使命だと考えています。だからこそ、志ある企業や人々と手を取り合い、日本のサステナビリティを現場から変えていくことが、今の自分が果たすべき役割だと捉えています。
求めている条件
上記課題を解決するためには、以下のような領域において実行力と技術力を持つパートナーとの連携が必要です。 まず、製品導入の現場となる食品製造・包装の現場を有するパートナーとの連携は不可欠です。容器としての実用性やライン適合性を検証し、PoCから量産までをスムーズに接続できる体制を構築するためには、食品工場・セントラルキッチン等を持つ企業との協力が重要です。 次に、当社が今後開発を予定している環境トレーサビリティプラットフォームの実装を進める上では、AI・IoT・LCA計測の知見を持つIT・環境系パートナーとの共創も必要です。 また、社会的インパクトを高めるためには、ESGに積極的な大手流通企業や自治体との連携により、堆肥化・循環モデルの普及促進を進めていくことが望ましいと考えています。 こうした複数領域の専門性をつなぎ、素材→製品→廃棄→循環→評価→発信までを一体で進められる“伴走型パートナー”との出会いが、事業化を飛躍させる鍵になると考えています。
企業情報
- 企業名
- 株式会社グリーンソリューション
- 事業内容
- 生分解性プラスチック事業、環境トレーサビリティ・プラットフォームの開発準備
- 所在地
- 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 20階
- 設立年
- 2024年
プランのアップグレードで企業情報をご確認頂けます
プラン詳細はこちら