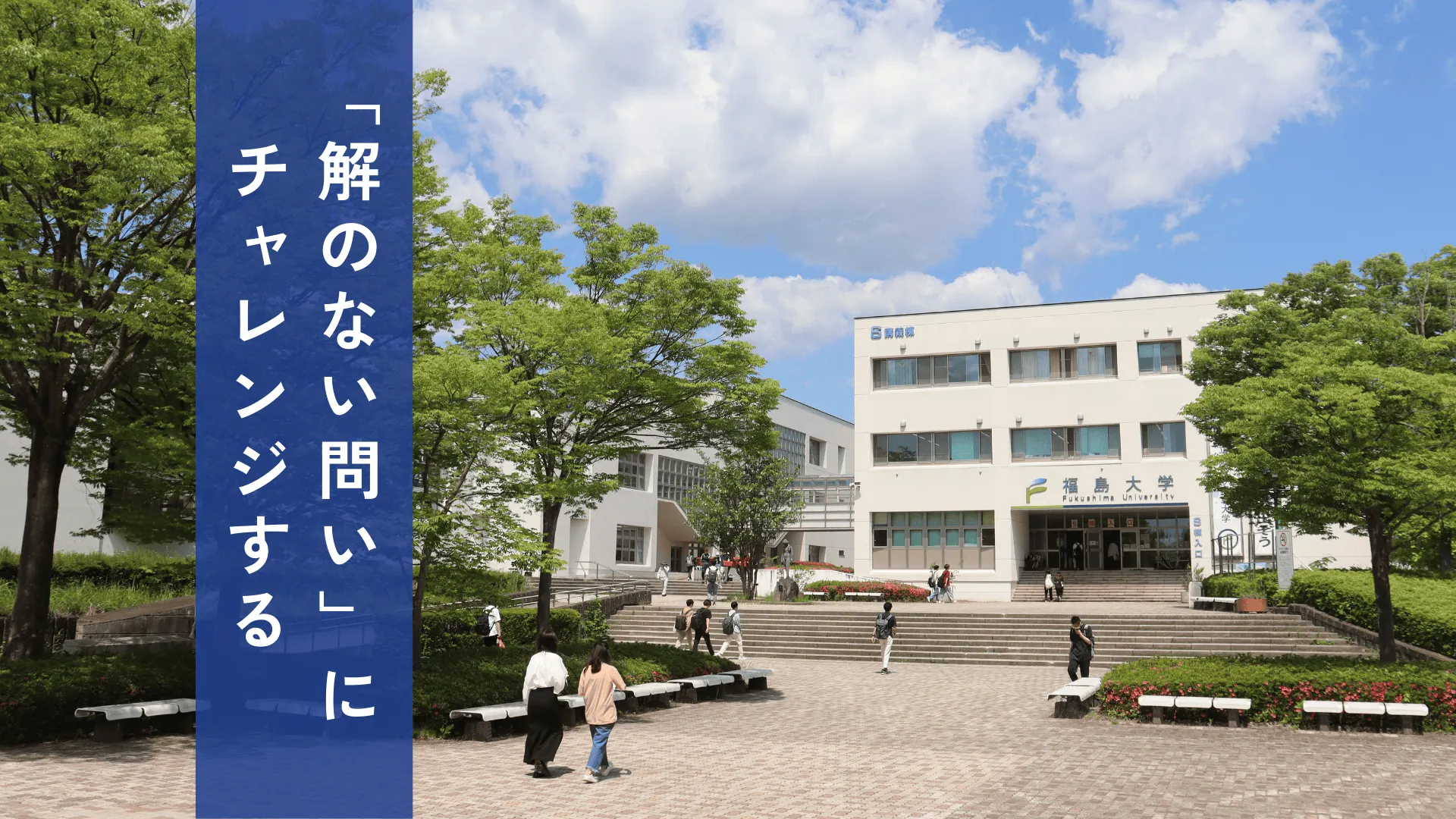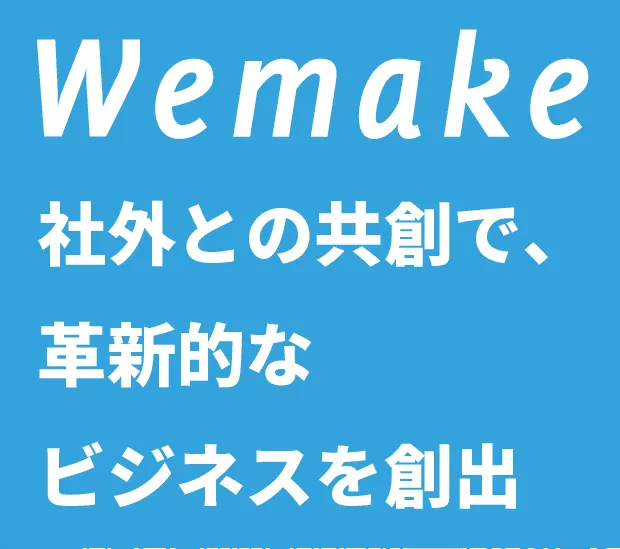- 更新:2025年07月22日
- 返信率:100%
福島県唯一の国立大学にて、地元エリアにおける高い信頼を誇る福島大学。 大学教員の知財・ノウハウを社会実装し、社会課題解決に取り組む共創パートナーを求めています。
国立大学法人 福島大学

- 発酵
- 新エネ技術
- 地域活性化
- 共同研究
- リソース提供(既存技術の提供・特許流用の検討など)
- 事業提携
- ジョイントベンチャー設立
- 教育研究機関
プロジェクトメンバー
責任者
プランのアップグレードで企業責任者情報を確認いただけます
プラン詳細はこちら
自社特徴
私たち福島大学地域未来デザインセンター(CFDC)は、福島大学の教員が保有する研究シーズと地域の社会課題を紐づけ、課題解決に資するプロジェクトを生み出すことを目指す機関です。
教員とは常に連携できる体制をとっており、約240名もの教員の研究シーズのみならず、その人柄も把握しながらプロジェクトを創り上げることがひとつの特長です。
福島には震災以来、多数の復旧・復興プロジェクトが生まれ、当センターの前身機関が誕生しました。以来10年あまりが経過し、復旧から復興へ軸足が移ってきた、2022年4月に名称も改め、当センターが設立されました。
地域の課題解決に向け、対話型協働にて自治体や企業、研究者、学生がフラットに議論しプロジェクトを創出する、そんなオープン・イノベーションの推進を私たちは目指しています。
提供リソース
■自治体、地元企業とのネットワーク
福島県唯一の国立大学として、県内自治体や企業に多数の卒業生を輩出しています。
企業や自治体、地域住民からの認知度や信用力も高く、政府、地方公共団体、金融機関、企業等様々な組織・機関とのネットワークを有します。
https://www.fukushima-u.ac.jp/university/efforts/agreement.html
■240+の現役教員・研究者、4,000+の在学生、50,000+のアルムナイの存在
■大学シーズの事業化支援スタッフ
■大学の保有する施設(環境放射能研究所、水素エネルギー総合研究所、発酵醸造研究所)
解決したい課題
「地域の未来は地域が決め、イノベーションも地域から生み出す」ために、大学教員が有する研究シーズを活用していきたいと考えています。
一方で私たちの最大の課題は、事業構想力、CxO人材、流通チャネルといったリソースや、事業を興す経験やノウハウが圧倒的に不足していることです。
今回の共創では民間企業様の知見・リソースとともに、本学の研究シーズを事業として成立させ、日本の地域活性化や社会課題解決につなげたいと思っています。
共創で実現したいこと
以下の研究テーマに即した事業化、社会実装に取り組みたいと考えています。
(1)理工系研究テーマ:髪の毛1本からストレスチェック
毛髪には、身体にいつ何がどのように起こったか、そしてそれについてどのような精神活動がどのように生じたか…という情報が、その毛細血管を通して、時々刻々と詳細に書き留められ、保存・記録されています。この情報を、毛髪を対象とするイメージングの独自技術を用いて可視化・表示します。
<共創イメージ事例>
医療や保健から、美容や食品、さらにはこれらに関連する保険・金融など、幅広い産業分野への高度な展開・応用につなげたいと考えています。
<参考リンク>
https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20250115/6050028447.html
https://gakujyutu.net.fukushima-u.ac.jp/015_seeds/seeds_187.html
https://www.agri.fukushima-u.ac.jp/topics/013498.html
(2)農学系研究テーマ:三次元再構築技術を核とした果樹樹形情報のアーカイブの開発
桃などの果実栽培技術向上や果樹園経営の安定化の手段として、果樹園をカメラでくまなく撮影し、コンピューター上で立体化する3D果樹園に取り組んでいます。園地や桃の樹形情報をデジタル化しアーカイブ・管理し、糖度分布などのデータを蓄積。これを栽培手法へフィードバックします。
<共創イメージ事例>
・果樹農家向けの新しい学習・評価ツール、生産性向上ツールとしてサービス化
<参考リンク>
(3)人文社会系研究テーマ:災害時の避難所運営を舞台にした防災研修(さすけなぶる)
『さすけなぶる』は東日本大震災・ふくしまの教訓を避難所運営で実際に起きた問題を解決していきながら学ぶワークショップ型防災教育ツールです。災害・地域・人、様々な要因によって変わっていく状況に臨機応変に対応していかなければならない災害時の考え方が身につきます。
<共創イメージ事例>
・スタディツアー等を提供している旅行代理店
・研修コンテンツの提供
<参考リンク>
求めている条件
・理工系…地方自治体、分析関連企業、医療・保健・美容分野を含むものづくり及びサービス関連企業、金融保険関連企業
・農学系…農業者・農業団体、農業・食品周辺産業
・人文社会系…自治体、民間企業、教育機関ほか
その他、弊社の事業にご興味をお持ちいただける企業様とは
さまざまな可能性を探索していけたらと思っております。
こんな企業と出会いたい
ビジネス領域
- 地方創生
- AgriTech
- 研修サービス
- 水素エネルギー
- 醸造
- 発酵
- 原子力技術
- 生産技術
- 測定分析技術
オープンイノベーション実績
▼ORENDA WORLD、福島大学、葛尾村の3社協定(2024.10)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000101429.html
▼日本政策金融公庫と包括連携協定を締結(2024.12)
https://cfdc.net.fukushima-u.ac.jp/information/activity/013510.html
企業情報
- 企業名
- 国立大学法人 福島大学
- 事業内容
- 寄付金を除く外部資金(受託研究・事業、共同研究)は、43億円/866件です。 科学研究費の獲得は、1.7億円/109件です。 (ともに2023年度)
- 所在地
- 福島県福島市金谷川1番地
- 設立年
- 1949年
プランのアップグレードで企業情報をご確認頂けます
プラン詳細はこちら