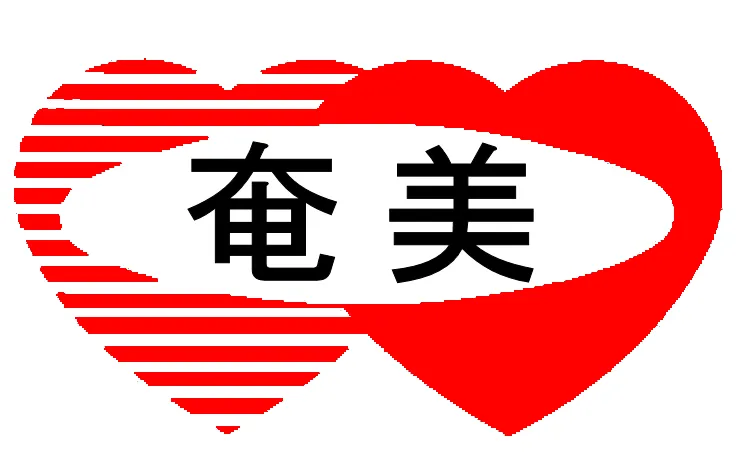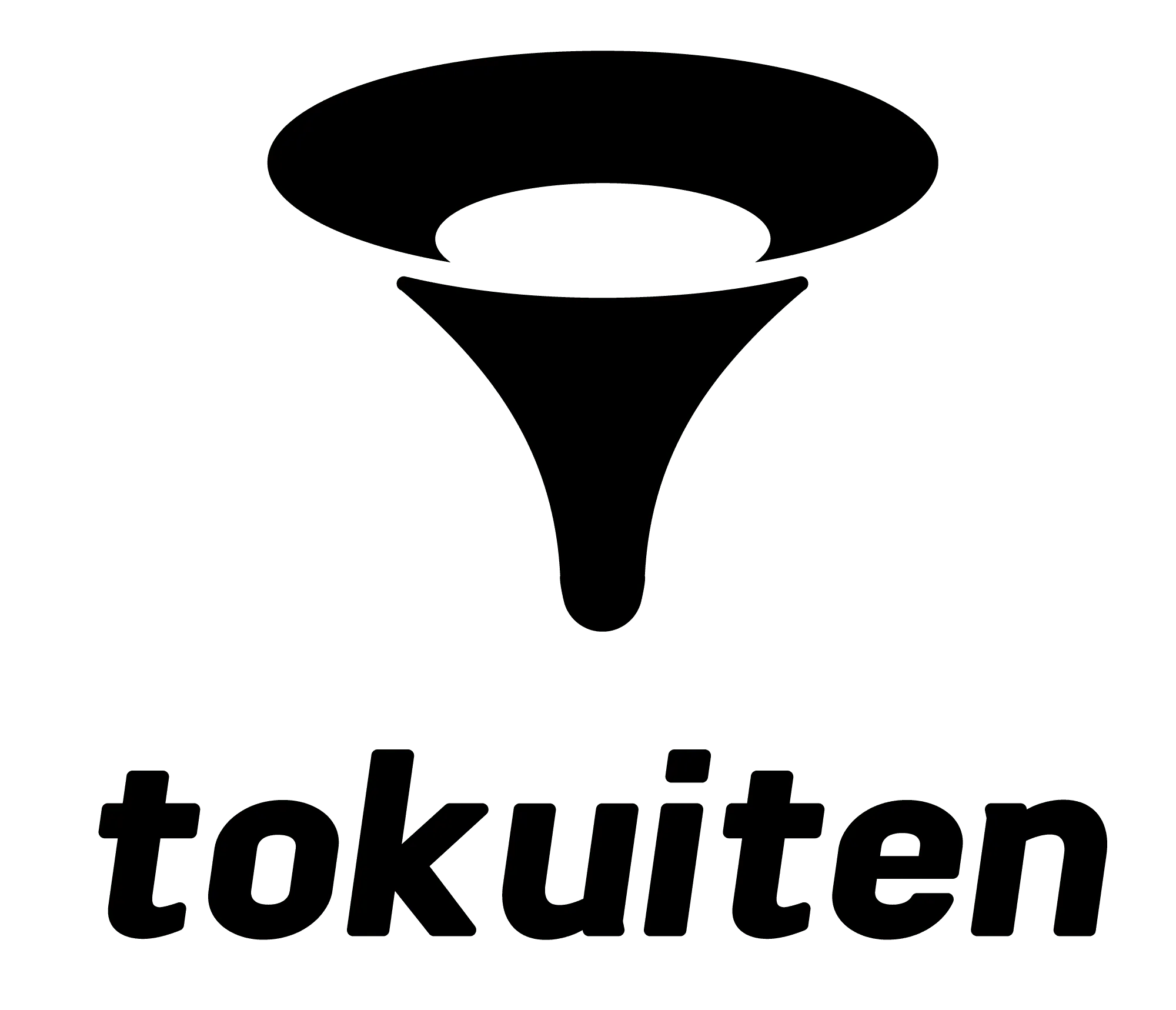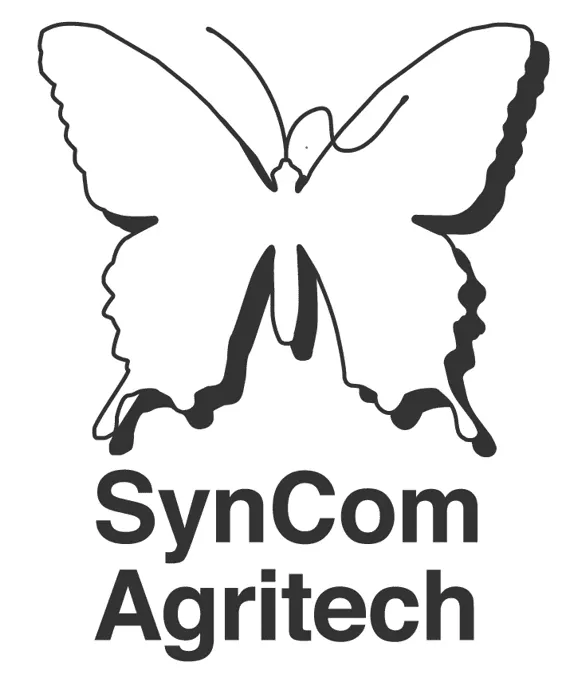- 公開:2024年05月17日
- 更新:2024年05月17日
meet ▶[いかす]:美味しい野菜が未来の地球と子どもたちを救う――いかすが目指すこれからの有機農業とは
株式会社いかす

- 課題解決No.13「気候変動に具体的な対策を」
- 地球温暖化対策
- 地域活性化
- 事業提携
- 資金調達したい
- ピッチイベント実施
- ネットワーキング
- 6カ月以内の提携希望
- スタートアップ
環境意識・健康志向の高まりを受け、有機野菜をはじめとするオーガニック食品が注目を集めている。しかし、実際の生産現場では、まだまだ農薬や化学肥料を使った農業が一般的であり、有機野菜を求める消費者ニーズとの間に乖離が生じている。
そのような状況の中、平塚市を拠点に農業を営む株式会社いかすは、有機農業による野菜の育成・販売にとどまらず、有機農業を志す就農者の支援・育成や、地域を巻き込んだネットワークの構築を推進することで、有機農業で育てた美味しい野菜の普及拡大を推進している。
また、同社は緑肥によって炭素を貯留する土壌づくりを行っており、2022年には、「カーボンニュートラルの実現」をサスティナビリティポリシーに掲げる日本テレビとの資本提携を実施している。
eiiconのオリジナルピッチ企画「eiicon meet up!!」登壇企業に話を聞くインタビュー企画『meet startups!!』。――今回は、株式会社いかす 代表取締役 白土卓志氏への取材を実施し、起業の背景や同社の有機農業の特徴、今後の展望について語っていただいた。
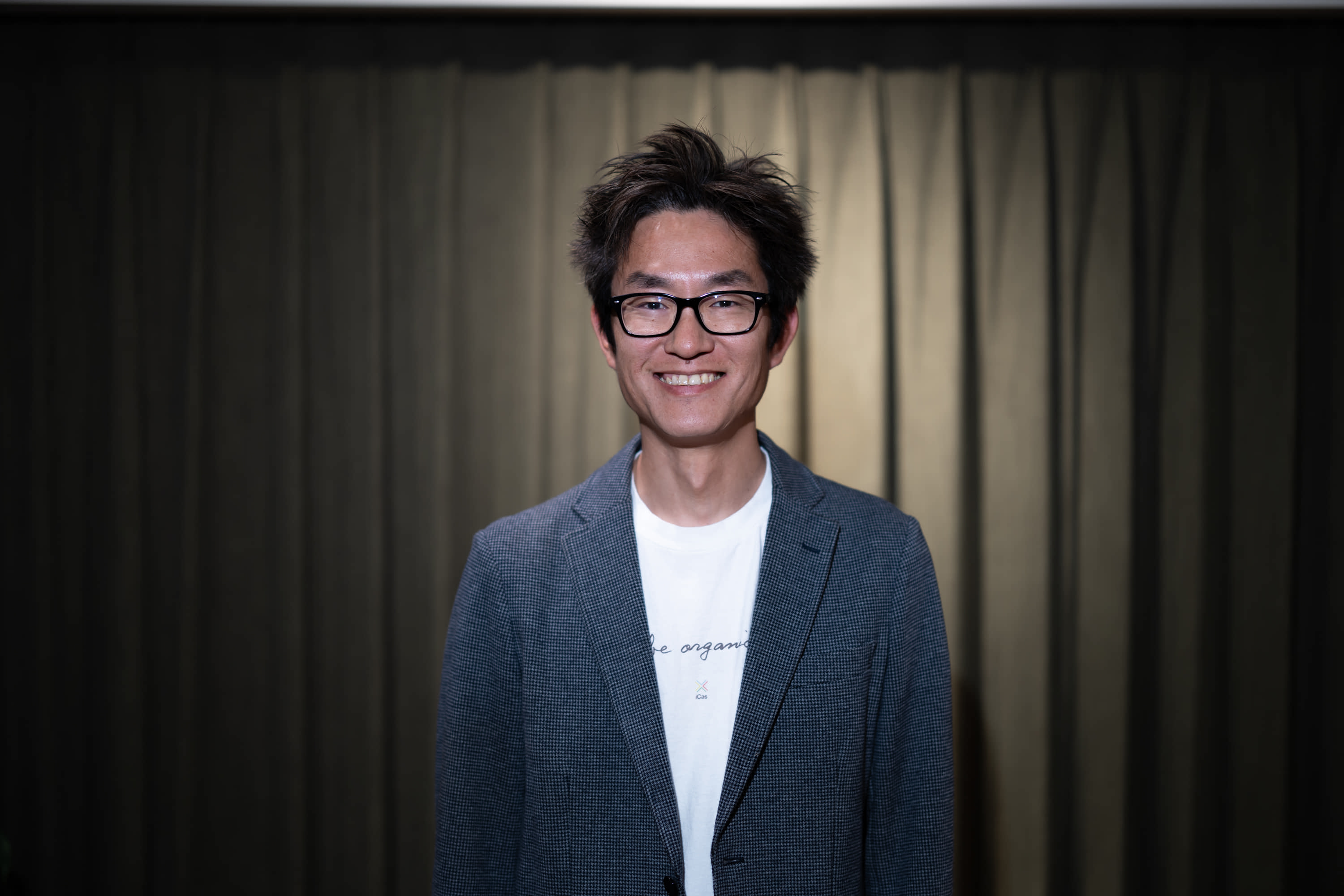
▲株式会社いかす 代表取締役 白土卓志氏
東京大学工学部卒業後、株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア株式会社)に新卒入社し、300名だった社員が4000名になるステージを経験。その後、仲間と人材サービスの会社を起業。31歳のときに、農業大作戦スタート。2015年に株式会社いかすを創業し、現在に至る。
※いかす PRページ https://auba.eiicon.net/projects/39376
#課題解決No.13「気候変動に具体的な対策を」 #地球温暖化対策 #地域活性化 #販売パートナー募集(チャネル拡大・エンゲージメント向上) #事業提携 #資金調達したい #ピッチイベント実施 #ネットワーキング #6カ月以内の提携希望 #スタートアップ
炭素循環農法で育った美味しい野菜を世界に広めるために
――まずは、白土さんのキャリアについて聞かせてください。
白土氏 : 大学卒業後、人材サービス会社の株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア株式会社)に入り、300名規模だった社員が4000名になる過程を経験しました。その後、リーマンショックがあった2009年にインテリジェンスを辞め、同期の仲間3人で看護師向けの人材紹介サービス会社を起業したのですが、その時期に農業を巡る様々な出会いがあり、2015年に株式会社いかすを創業しました。
――農業を始めることになった経緯も教えてください。
白土氏 : 私は大学時代に、自分のこれからの人生のビジョンを明確にするための未来日記を書いていました。あるとき、その未来日記を読み返す機会があったのですが、31歳時点でのなりたい姿として「農業大作戦」と記されていました。なぜ、大学時代の私が「農業大作戦」と書いたのかはまったく覚えていないのですが(笑)、その出来事をきっかけに農業について興味を持って調べるようになったのです。
――「農業大作戦」という言葉にピンときたということでしょうか?
白土氏 : 未来日記を読み返した時期と私が会社を辞めることを考え始めた時期が重なっていたことも大きかったのかもしれません。私は麻布中学、麻布高校、東大を経てインテリジェンスに入ったのですが、ずっと誰かとの勝負や競争が続く世界で生きている感覚がありました。そのような世界にも楽しい側面はあるのですが、一方では「こんな競争がいつまで続くのだろう…」と、違和感を抱き始めてもいたのです。
そんな思いを抱えていた時期だったからこそ、自分が大学時代に書き留めていた「農業大作戦」という言葉に運命的なものを感じたのかもしれません。農業も資本主義のシステムの一部ではありますが、他の産業とは時間の流れ方が違いますし、人との競争以前に自然を相手にすることが重要な世界ですからね。
――農薬や化学肥料を使わない有機農業を行うことになった理由についても教えてください。
白土氏 : 「農業大作戦」にピンと来て、農業についていろいろと調べたり、知り合いの農家に話を聞いたりしている中で、炭素循環農法というものに出会いました。現行の農業の9割型は窒素を意識した農法で行われており、炭素を意識した炭素循環農法に取り組んでいる農家はほとんどいません。現在の農学では、炭素を畑に入れると増えてしまう糸状菌を排除することが常識とされているからです。
しかし、そんな異端とも言える炭素循環農法で育った野菜は、甘味があってエグ味が少ない。つまり、途方もなく美味しいのです。私は炭素循環農法で育った有機野菜を初めて食べたときに大きな衝撃を受け、「これを世界に広めていきたい」と考えたのです。
「育む」と「食べる」がバランス良く循環する地域環境を構築中
――いかすの事業内容について教えてください。
白土氏 : 有機農業の「はぐくむ事業」を軸に「たべる事業」「あそぶ事業」「まなぶ事業」「めぐる事業」という5つの事業を展開しています。現在は、宅配や卸・スーパー等での販売を通じて皆さんに野菜を提供する「たべる事業」が売上の約8割を占めています。
当社の場合、広告などは一切出していませんが、私の講演や友人紹介などをきっかけに、毎年2、3割ずつ購入者が増えています。また、お試し品を購入した方の4〜5割程度が定期購入者になるなど、お客様の数は順調に増え続けています。
これらの「たべる事業」を通して当社の野菜を食べていただいた後、実際に畑に来てみたいと考える人のために「あそぶ事業」があります。畑に来て遊んでみて、今度は自分でも野菜を育ててみたいと考える人には「まなぶ事業」を提供しています。
当社が運営する畑の学校「テラこや」で学ぶ農業研修生となり、その後に農家として独立する人もいますし、当社の社員になる人もいます。実際に当社のメンバーは、役員以外の全員が「畑の学校」の卒業生です。

▲いかすは、神奈川県平塚市出縄地区に農場を作り、活動の拠点としている。
――「めぐる事業」で展開されている「湘南オーガニックタウン構想」についても教えてください。
白土氏 : 私たちが平塚市で農業をスタートした当時から市の農業関係者の方々に賛同いただいている取り組みであり、言葉の通り湘南をオーガニックな地域にすることを目指しています。
何かを急激に変えるというよりも「街のスーパーにも普通に有機野菜が置いてある」といったイメージで、有機野菜や無農薬の畑が地域や人々の生活の中に少しずつ溶け込んでいき、いつの間にか「当たり前のもの」になっているような状況を作りたいと考えています。
そのような世界観を実現するためには、有機野菜の生産者を増やしていく必要がありますが、現状ではまだまだ有機農業にチャレンジする農家が少ないため、今後も当社が運営する畑の学校などを通じて新規就農者を増やしていく方針です。
また、新規就農者の畑で収穫した野菜を当社で買い上げ、当社経由で販売していくようなパートナー制度を立ち上げるなど、有機野菜を育むことと食べることに関して、地域内でバランス良く循環していけるような環境を構築している最中です。
――そのような取り組みの成果はいかがでしょうか?
白土氏 : 全国での有機野菜のシェアは、市場に出回る野菜の0.6%程度に過ぎません。しかし、現在の平塚市では3〜4%程度にまで向上しているなど、少しずつではありますが取り組みの成果が現れ始めていると感じます。
カーボンニュートラル実現に貢献する炭素貯留型の畑を増やしていく
――今後、どのような企業や団体との協業・オープンイノベーションを考えていますか?
白土氏 : 当面はスーパーマーケットや自然食品店など、当社やパートナーが育てた有機野菜を販売いただける企業様の開拓に注力していきます。また、最近では平塚市周辺の小中学校の子どもたちが畑に遊びに来たり、一緒に農業を学んだりする機会が増えているので、今後も「食育」をテーマとするような取り組みができる企業・団体・学校との協業を増やしていきたいと考えています。
さらに将来的には、産婦人科や助産院のような出産・育児に関係する病院などと協業し、子どもを産み、育てるための健康な身体づくりのために有機野菜を活用いただくような展開も考えています。
私たちは「未来の地球と子どもたちのために」という理念を掲げているので、これからの地球環境や子どもたちの未来に貢献できるような協業・共創であれば、様々な可能性にアプローチしていくつもりです。

▲有機野菜をふりかけにして販売するなど、いかすでは新たな事業にも積極的に着手している。
――2022年11月には日本テレビと資本提携を行うなど、インパクトスタートアップとしての取り組みも注目されていますが、その点も踏まえて今後のビジョンや事業展望についてお聞かせください。
白土氏 : 私たちが取り組んでいる農薬・化学肥料を使用しない有機農業は、土壌の改善を通して自然環境の再生を目指すリジェネラティブ農業(環境再生型農業)でもあります。一般的な畑は炭素を排出する側ですが、私たちの畑は土壌内に微生物を飼うことで炭素を貯留しています。
そのため私たちの事業や畑はカーボンニュートラル実現への貢献が期待されており、実際に土壌診断を行うことでインパクトの数値化・見える化も行っています。今後はパートナー制度などを通じて当社の畑で行っている取り組みを拡大しながら、有機野菜の収穫増とカーボンニュートラルへの貢献を推進していく方針です。
また、私たちが畑を作る際に使っている緑肥(植物を活用した肥料)は、誰もが簡単に使えるものであり、コストが高いわけでもありません。アジアやアフリカの貧しい地域でも手軽に導入できる肥料なので、日本国内にとどまらず世界各国に広めていくなど、グローバルでの事業展開も視野に入れながら動いていくつもりです。

▲2024年3月に開催されたピッチイベント「eiicon meet up!!vol.10」に登壇した白土氏。
(編集:眞田幸剛、文:佐藤直己)