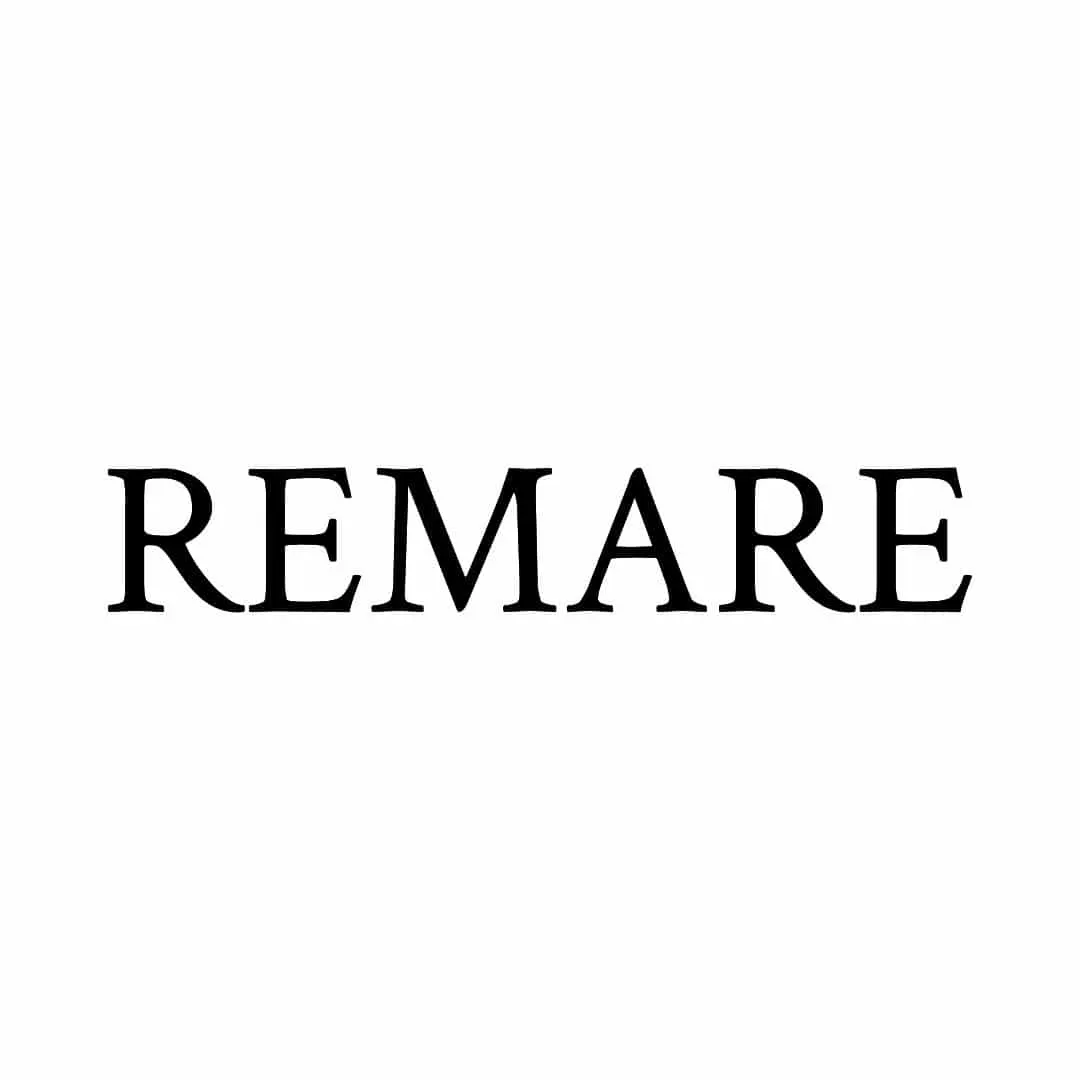- 公開:2024年12月25日
- 更新:2024年12月25日
3期目を迎える富士市の「CNFオープンイノベーション促進事業」――多様な素材・技術を持つ富士市CNFプラットフォーム会員4社(エフピー化成工業/第一工業製薬/日本食品化工/富士木材)が参画!実現したい共創事業とは?
エフピー化成工業株式会社

- ファイバー
- 再生資源
- リサイクル
- 中小企業
静岡県富士市は、富士山麓の豊富な水資源や木材を活かして多様な産業を発展させてきた。特に製紙産業が盛んな「紙のまち」として知られてきた同市だが、次世代を担う産業として「セルロースナノファイバー(以下、CNF)」を活用した新たな取り組みを進めている。
2019年3月には「富士市CNF関連産業推進構想」を策定し、CNFの実用化支援や用途開発の加速、関連産業の創出を目指して「富士市CNFプラットフォーム」を設立。産学金官等の連携によるネットワーク構築が進められている。プラットフォームの会員数は、2024年11月現在において213(企業・団体等186、個人27)に達し、「CNFでつながる」場が形成されつつあるという。
そんな富士市とeiiconは、2022年11月にパートナーシップを締結。eiiconが提供する日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」を活用した、「富士市CNFプラットフォーム」の普及啓発と用途開発を進めるほか、プラットフォーム会員企業を代表して複数社に、共創支援を行っている。
2022年より開始した本事業(デジタルツールを活用したCNFオープンイノベーション促進事業)は、今回で3期目。2024年度は、4社(エフピー化成工業/第一工業製薬/日本食品化工/富士木材)が「AUBA」を活用したオープンイノベーションに取り組むことになり、共創パートナーを募集している。そこでTOMORUBAでは、主催者である富士市と参加企業4社にインタビューを実施し、この活動への意気込みやオープンイノベーションを通じて実現したいことを伺った。
【富士市役所】 (富士市CNF)プラットフォーム会員企業の次の一手を、オープンイノベーションで切り拓く

▲富士市役所 産業交流部 産業政策課 CNF・産業戦略担当 主幹 平野貴章 氏
――まず、富士市が「デジタルツールを活用したCNFオープンイノベーション促進事業」に取り組む背景からお聞かせください。
富士市・平野氏: この事業を始めたきっかけは、コロナの影響で、CNFに取り組む市内のものづくり企業が、展示会への出展や見込み顧客との面談の機会を失ったことでした。この状況を打破するために、新たな形で取り組む必要があると考えました。また、デジタルトランスフォーメーション(DX)も注目されていましたから、DXの要素を取り入れて、市内企業の皆さんに新しいビジネススタイルを切り開いてほしいという思いから、この事業を始めたのです。
――これまで2年度にわたり本事業を推進してこられました。2年目を終えて3年目に入ろうとする現時点での手応えについてお聞かせください。
富士市・平野氏: 2年目は、1年目の成果を見た企業が参加したことが印象的でした。参加企業は「自分たちは何をすべきか」「どんなことができるか」を、ある程度理解した上で、自ら手を挙げてくれました。そのため、1年目の企業よりも積極的に「AUBA」を活用していただいたと感じています。
参加企業からは「こんな企業と出会えた」「異なる領域の方からアプローチがあった」という声が多く寄せられています。自社では想像できなかった発想やアイデアを持つ企業と、「AUBA」を通じて出会えたことが大きな成果だったと感じています。また、eiiconさんの手厚い支援のおかげで面談率も向上し、イノベーションを進めたい企業の動きが加速したと思っています。
――これまでの取組のなかで、特に印象に残っている事例は?
富士市・平野氏: 印象に残った事例を2つ挙げると、まず1つ目は(トイレットペーパーなどの)衛生用紙類を製造する「丸富製紙」です。同社は「AUBA」を積極的に活用したことで、新しい自社の課題が見えてきたそうです。その課題を解決してからオープンイノベーションを進めるという展開をされました。もし、「AUBA」を利用していなければ、その課題に迅速に気づけなかったかもしれません。そうした観点で、良い取組になったと感じています。
2つ目は、段ボール製造大手の「レンゴー」です。同社は富士市の企業ではありませんが、逆にそれが興味をもってもらえるキッカケとなり多くの情報が集まりました。また、大企業としての発信力もあり、色々な場所で「AUBA」を通じて得た効果を、広く発信していただけました。製紙業界の方たちが、中堅・中小企業やスタートアップ、異分野・異業種との出会いを通じて、新しい発想やつながりを得られた点が良かったと思っています。

――「AUBA」というオンラインプラットフォームを使うことで、富士市が普及に取り組むCNFの知名度が、全国的に高まってきたという実感はありますか。
富士市・平野氏: CNFの認知は徐々に広がっていると感じます。セミナーやイベントでは、元々CNFに興味を持った人しか集まってくれません。一方、「AUBA」であれば、CNFに興味がなかった層や異なる領域の人たちにも、知ってもらうことができます。他の方法では難しかったことが、「AUBA」では実現できていると感じますね。
――CNFに無関心だった層にも発信できているということですね。3年目となる今年度は、4社(エフピー化成工業/第一工業製薬/日本食品化工/富士木材)がホスト企業として参加され、「AUBA」を使ったオープンイノベーションに挑みます。この4社を採択した背景や期待は?
富士市・平野氏: 「エフピー化成工業」は、プラスチック関係の優れた材料と出口(販路)をお持ちですが、さらなる成長には多様なパートナーとの連携が重要だと感じます。「AUBA」を使って新たなビジネスの切り口を見つけていただければと思います。「第一工業製薬」は、昨年度のレンゴー社と同様に、CNFの供給メーカーとして研究開発力と営業力をお持ちです。自社の技術を、どのようなパートナーに展開するかを探るためのツールとして、「AUBA」が有効なのではないかと思います。
「日本食品化工」は、富士市内の大企業で研究所も構えておられます。でん粉を活用した事業を展開され、CNFを含め、バイオマスという点で、親和性は高いでしょう。CNFとでん粉を組み合わせた事業展開や、でん粉の工業的な用途を探るために、「AUBA」を活用していただければと思っています。「富士木材」は、市内の中小企業で、自社内で板紙製品に関する製造や加工を行っておられますが、自社単独だけでは限界もあると思います。「AUBA」でパートナーを見つけ、新しいアイデアやつながりを生み出し、オープンイノベーションで事業を進展させてほしいです。
――最後に、「デジタルツールを活用したCNFオープンイノベーション促進事業」を今後、どのように発展させていきたいのか。富士市のビジョンをお聞かせください。
富士市・平野氏: まず、この3年間で参加した12社には、オープンイノベーションをさらに深め、自社のビジネスや人材育成に積極的に活用してほしいと考えています。また、事例が蓄積されてきたので、それを横展開していくことも重要だと思っています。市内企業の皆さんにオープンイノベーションを知っていただき、今後の事業展開に役立ててもらいたいです。さらには、CNFやセルロースといったバイオマス素材を、日本中の方たちに認知してもらい、炭素循環社会やサーキュラーエコノミーの実現につなげたいですね。
【エフピー化成工業】 新素材「グリーンチップ® CMF®で創造する循環型社会の新たな体験!

▲エフピー化成工業株式会社 管理部 兼 営業企画部 課長 望月彩実 氏
――最初に、御社の事業内容や望月さんの担当業務を教えてください。
エフピー化成・望月氏: 当社代表はもともと紙管メーカーの社長を務めていましたが、そこで難古紙と樹脂を混ぜ「FPC」というハイブリッド樹脂を作る技術を確立しました。この技術を持って2018年に独立し、当社を設立。その後、同じ混ぜる技術を応用して、巴川コーポレーション社と共同開発したのが、今回のテーマでもある「グリーンチップCMF」です。私は経理職として入社しましたが製造現場も手伝いますし、最近は一般事務や営業サポートも担当しています。まさに「何でも屋さん」です(笑)
――「デジタルツールを活用したCNFオープンイノベーション促進事業」には、どのような理由から参画することになったのですか。
エフピー化成・望月氏: 自分で言うのもなんですが、この「グリーンチップCMF」という素材は非常に優れています。にもかかわらず、実績がないため、なかなか採用されないのが現状です。この事業に参加することで、もしかしたらこの新素材を普及させるチャンスが広がるかもしれないと期待し、参加を決めました。
――御社の「グリーンチップCMF」の特徴について教えてください。また、それを用いて、どのような共創を実現したいとお考えですか。
エフピー化成・望月氏: 「グリーンチップCMF」は、マテリアルリサイクルが可能な素材です。日本では、燃やしてエネルギーにするサーマルリサイクルが主流で、化学的に分解して原料に戻すケミカルリサイクルなども開発が進んでいますが、これらはコストが高かったり、多くのCo2が発生したりといった問題もあります。
対して、マテリアルリサイクルは使用後に破砕して再利用できるため、非常に環境に優しいのです。こうした素材はまだあまり普及していないので、広めていきたいと考えています。今回の共創では、「グリーンチップCMF」を通じて、循環型社会を体験してもらえるような活動を進めていきたいです。

▲大手化学メーカー、巴川コーポレーションと共同開発した「グリーンチップCMF」。幅広い成形性を有する環境に配慮したセルロースファイバー複合樹脂だ。
――どのようなパートナーと一緒に取り組みたいですか。
エフピー化成・望月氏: 消費者の手に直接届かなければ、素材の良さが認識されにくいと思います。例えば、自動車の内装部品の1つに使われても、それをリサイクルしている気持ちは湧かないでしょう。ですから、この素材の良さを消費者が体験できる形で、循環型社会を一緒に広めてもらえる企業と協力できたらと思っています。
ただ、難しいのが最先端技術で作られるセルロースファイバー複合樹脂は高価なため、商品価格自体も高くなること。日本では環境にお金を払う人がまだまだ少ないため、循環を体験できるストーリーも含めて、この素材の良さを理解してもらえるような場所で販売したいですね。
――現状、一般消費者向けにはどう展開されているのですか。
エフピー化成・望月氏: 現在、「Mawal(マワル)」というブランド名で、主にECサイトを通じて販売しています。また、住宅メーカーやセレクトショップからもお声がけをいただいていますし、2025年の春頃には実店舗での取り扱いも予定しています。主な製品は、お椀やお箸などの食器類です。食器を選んだ理由ですが、一般的に親水性のセルロースファイバーと疎水性のポリプロピレンを混ぜる際、添加剤を多く使う必要があります。
しかし、様々な添加剤を使用するとポジティブリスト制度(※)に適合しにくくなる為、食器として使用できなくなるのです。一方で「グリーンチップCMF」の場合は、添加剤を必要最低限しか使わない独自の方法で作っているため、食器にも使用できます。なので、安心・安全に使えるマテリアルリサイクルが可能な素材であることをアピールするため、食器を選んだのです。
※ポジティブリスト制度とは、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とする国の制度。

▲望月氏の手元や奥の棚にあるのが「Mawal」。お椀やスプーン、お箸といった商品がラインナップされている。
――共創で活用できる御社の強みには、どのようなものがありますか。
エフピー化成・望月氏: 当社の強みは技術力にあります。セルロースナノファイバーを含む樹脂は、一般的に流れにくいと言われていますが、当社はセルロースの繊維分布を変えることで、流れやすさを調整できる技術を持っています。また、材料から製品まで一貫して自社の工場で製造できる体制が整っており、射出成形機や押出成形機などの機械も保有しているため、プロトタイプの作成なども柔軟に対応できます。
――最後に、応募を検討しているパートナー企業に向けてメッセージをお願いします。
エフピー化成・望月氏: 「Mawal」のステートメントは、“捨てる”ことを“捨てる”なんですね。「グリーンチップCMF」は、リサイクルを繰り返しても物性が落ちない素材なんです。分野問わず何にでも使用できます。この素材の良さを、小さなことからでもいいので広める活動を進めていきたいと考えています。最終的には、世の中のすべての樹脂を「グリーンチップCMF」に置き換えることも視野に入れており、一緒に取り組んでくれるパートナーをお待ちしています。
【第一工業製薬】 1909年創業の化学メーカーが生み出したCNF「レオクリスタ」を活用。新製品の共同開発と実用化を目指す!

▲第一工業製薬株式会社 研究本部 研究カンパニー部 レオクリスタ・サステナブル材料グループ長 博士(農学) 後居洋介 氏
――御社は1909年に創業した化学メーカーで、界面活性剤を中心とした添加剤の製造に強みを持ちながら、CNF製品「レオクリスタ」やセルロース材料を開発・提供しています。環境やエネルギー、ライフサイエンスなど多岐にわたる分野で事業を展開されていますが、CNFはどの分野に注力されていますか?
第一工業製薬・後居氏: 現状、レオクリスタは化粧品や塗料・インク分野が中心ではありますが、様々な用途で開発中です。当社のCNF以外の製品においても、同じ製品でも環境エネルギー分野とライフサイエンス分野など、全く異なる分野に応用されたりしています。CNFも具体的な分野に縛られず、幅広い可能性を模索していますね。
例えば、電池材料分野では分散剤やバインダーとして利用される研究も進めています。また、セラミックス分野では高強度化を図るための材料として開発を進めています。このように、私たちは技術を通じて社会課題に具体的に貢献したいと考えています。
――さまざまな分野で活用できるCNFを開発されている御社ですが、今回、「デジタルツールを活用したCNFオープンイノベーション促進事業」に参画した理由についてお聞かせください。
第一工業製薬・後居氏: CNFは非常に新しい素材なので、通常の営業活動ではまだ見えていない可能性があると感じています。これまでとは異なる視点や業界の方々との接点を持つことで、新たな使い方や価値を発見できるのではないかと思い、参加を決めました。
加えて、社内外のさまざまな分野の方々と連携することで、自分の視野を広げるチャンスとも感じています。研究というと閉じられた環境での業務が多いですが、こうした取り組みで外部の方々と直接意見交換できる場は非常に刺激的です。
――オープンイノベーションに取り組むにあたって核となるのがCNF製品「レオクリスタ」やその他のセルロース材料です。後居さんは「レオクリスタ」の”生みの親”とも伺いましたが、この製品の強みや特徴を教えてください。
第一工業製薬・後居氏: 「レオクリスタ」は、少量添加するだけで性能を大幅に向上させられる点が大きな特徴です。私たちは添加剤に強みを持つメーカーとして、他社の製品に付加価値を与える技術に長けています。「レオクリスタ」もその延長線上にある製品です。
具体例を挙げると、化粧品分野では金箔や微粒子を均一に分散させることで安定性を高める用途や、塗料、インク分野では粘性、流動性の制御などの用途で使用されています。これらの分野では、これまで難しかった「スプレーによる塗布が可能でありながら、ゲル状であるためにタレ落ちない」製品づくりにも貢献しています。こうした事例を見るたびに、「レオクリスタ」の可能性が広がっていると実感します。

▲高い増粘性と沈降防止効果、スプレー可能でタレないゲル、水を除去するとセルロース繊維同士が強固に絡み合った皮膜になるなど、「レオクリスタ」は多くの特徴を持つ。化粧品や塗料・インクといった分野での活用が進んでいる。
――共創を通じて、どのようなことを実現したいとお考えですか?
第一工業製薬・後居氏: 環境配慮製品の開発を目指すべく、当社が保有するセルロース材料や「レオクリスタ」などを活用した共創に取り組みたいと思います。私たちはBtoB事業がメインのため、BtoC領域で製造・販売のリソースを保有するパートナー企業と日用品などの製品開発や、素材メーカーさんと環境配慮素材の共同開発にも挑戦してみたいと考えています。ただ、これはイメージの一例です。アイデアベースのディスカッションから共創の可能性を探索できれば嬉しいです。
――御社はこれまでもさまざまな企業と共同開発を進めてきたとお聞きしました。具体的にどのような取り組みをされてきたのでしょうか?
第一工業製薬・後居氏: 一例として挙げさせていただくのは、文具メーカーの三菱鉛筆社との事例です。三菱鉛筆社とはボールペンの新製品開発を進め、最初にサンプルを提出したのが2012年頃。実際に市場で販売されるまで約3〜4年かかりました。ゲルインクボールペンにおける理想的なゲル化剤としてレオクリスタの機能に注目していただき、三菱鉛筆社の筆記具開発で培った超微粒子顔料分散技術と掛け合わせたのです。安定性や書き心地を犠牲にしない設計を実現するために、細かな調整を行い、商品化を実現しました。

――ありがとうございます。ますますCNFの可能性に期待が膨らみました。最後に本事業にかける意気込みと応募企業へのメッセージをお願いします。
第一工業製薬・後居氏: 本事業では、参加企業の皆さんと「これ、面白いですね」と感じられる瞬間を共有し、それを起点に新しい展開を一緒に生み出していけたらと考えています。
新製品の開発には「試してみたけれど思った通りにいかなかった」といった壁がつきものです。しかし、そこで諦めるのではなく、「もう少し試してみたい」「これをどうにか活かせないか」と粘り強く向き合ってくださる企業が、最終的には製品化まで持っていくケースが多いと思います。
私たちも一緒になって、そうした挑戦を全力で推進します。うまくいかないことがあっても、そこに可能性を見出して一緒に考え、めげずに取り組んでいける方々と出会えることを期待しています。
【日本食品化工】 トウモロコシ由来のでん粉糖を活用し、代替プラスチック領域に新規参入!

【写真中】 日本食品化工株式会社 研究所 研究二課長 高口均 氏
【写真左】 日本食品化工株式会社 研究所 研究二課 相沢健太 氏
【写真右】 日本食品化工株式会社 研究所 研究二課 村松大輔 氏
――まず、御社の事業概要や「デジタルツールを活用したCNFオープンイノベーション促進事業」に参画した理由からお伺いしたいです。
日本食品化工・高口氏: 当社は、トウモロコシ由来のでん粉や糖を使用した素材を生産しており、主に飲食品業界や製紙業界が取引先です。しかし、昨今は日本国内では人口が減少していますし、電子化が進むことで紙の需要も縮小傾向です。そのため、既存の領域から抜け出し、新しい領域に挑戦する必要性を感じています。加えて、持続可能な社会の形成に向けて当社の素材を活かせるのではないかと考え、この事業に参加することにしました。

――新たにプラスチック市場に参入されたそうですが、どのような動きをされているのでしょうか。参入してみての手応えはいかがですか。
日本食品化工・高口氏: でん粉を主原料としたプラスチック代替素材「スタークロス」を開発しました。この素材を食品容器や雑貨などで活用できないかと考え、全国規模での展開を始めています。お客様からは「代替プラスチック素材としてでん粉が使えそうだ」との声をいただいており、でん粉の大きな可能性を感じています。
――「スタークロス」の強みや特徴について教えてください。
日本食品化工・高口氏: 従来のバイオマス材料だと、型に流し込む際の流れが悪くて、途中で止まってしまうことも多いと聞いていますが、「スタークロス」は粒子状のでん粉がプラスチックに混ぜられているため、非常に滑らかで流れやすいことが特徴です。石油由来のプラスチックと同じように成形が可能で、耐久性も十分に出すことができます。
日本食品化工・相沢氏: お客様からは、流れにくさに加えて成形時のにおいや黄ばみも、バイオマス材料の課題だと聞いています。「スタークロス」は成形性が良好で、これらの課題も大幅に解決していますし、設備を傷めることもありません。
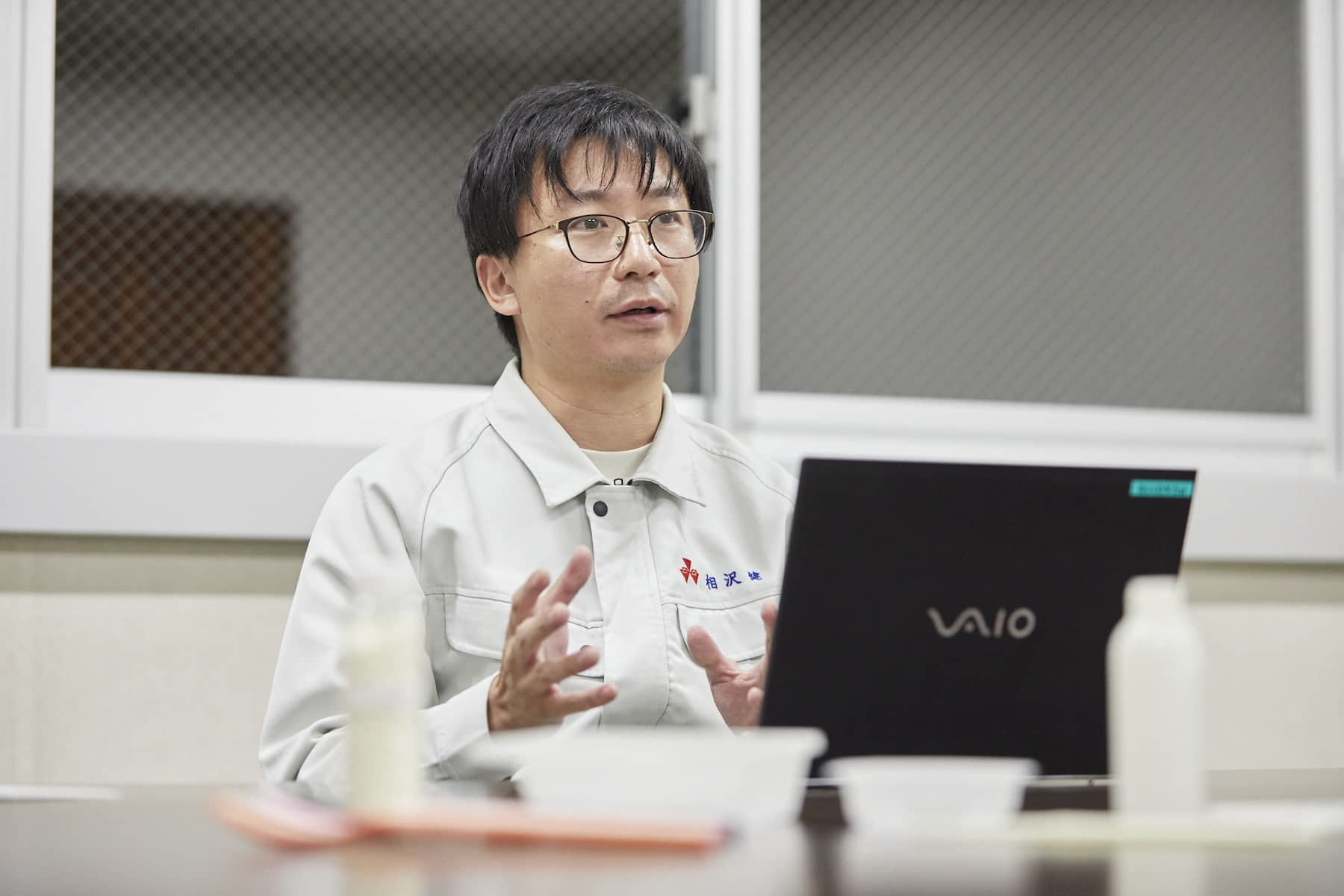
――なぜ、トウモロコシをプラスチック用途に使おうとお考えになったのですか。
日本食品化工・高口氏: お客様からの要望や政府の「石油由来のプラスチックを削減しよう」という方針を受け、トウモロコシを材料に新たな素材が作れないか試行錯誤を始めました。トウモロコシは全世界で効率的に栽培されているサステナブルな農作物で、セルロースと同様に安定的に大量供給が可能です。こうした点でも優れており、持続可能な社会の実現に貢献できると考えています。
――どのような企業と共創したいとお考えですか。
日本食品化工・高口氏: でん粉や糖を化学的に加工し、新しい材料として生まれ変わらせる技術を持つ企業と出会いたいです。また、「スタークロス」を使って成形をしてくださる成形メーカーともお話をしたいです。サステナブルな社会の形成に貢献したいという想いを持った企業であれば、当社と共創シナジーを高められるのではないかと思っています。

▲食品容器やスプーン、歯ブラシ、うちわなど、「スタークロス」を活用したさまざまな成形事例が生まれている。
――共創で活用できる御社の強みには、どのようなものがありますか。
日本食品化工・高口氏: 当社の強みは、大量のトウモロコシからでん粉や糖を高い精度で取り出せる生産技術にあると思っています。取り出した後の残滓も家畜の飼料などに使い、余すところなく活用しています。また、研究所には多くの研究員が在籍しており、でん粉や糖を多岐にわたって開発できる体制もあります。
日本食品化工・村松氏: でん粉や糖類はバイオマス素材で癖のある材料です。そのため、取り扱い経験の少ないプラスチック製造会社に検討頂く場合、でん粉や糖類のポテンシャルを上手く引き出せないことが多いです。しかし、当社はでん粉のスペシャリストとして、その取り扱いに長けており様々な加工ができます。

日本食品化工・高口氏: これまで、全国規模で飲料や食品、清酒メーカーなどと取引関係を築いてきました。こうした既存領域の販売網も、新しい製品を流通させる際に活用ができます。また、タイに関連会社があり、そのグローバルネットワークも利用可能です。
――最後に、応募を検討しているパートナー企業に向けてメッセージをお願いします。
日本食品化工・村松氏: でん粉は特殊な材料ですから、馴染みがない方も多いでしょう。まずは実際に触れていただくことが大事だと思います。ご連絡いただければ、私たちが全力でサポートしますので、ぜひ触れてみてほしいですし、さまざまな業界の方々に興味を持っていただけると嬉しいです。
日本食品化工・相沢氏: でん粉を積極的に活用し、新しい使い方を見つけてくれる企業とパートナーシップを築きたいと考えています。化学分野にも挑戦していきたいので、少しでも興味があれば、ぜひご応募ください。
日本食品化工・高口氏: 私自身、当社に入社する前は、でん粉や糖は食べ物だと認識していました。ですが、調べるうちに非常に面白い性質を持った物質だと気づきました。ぜひ、この面白さを一緒に開拓しませんか。
【富士木材】 地産ブランド「富士ひのき」等を核にした、革新的な新製品の開発を実現!

【写真左】 富士木材株式会社 取締役 包装資材事業部 部長代理 川口正訓 氏
【写真右】 富士木材株式会社 包装資材事業部 営業 鈴木俊樹 氏
――まず、御社の事業概要をお伺いしたいです。
富士木材・川口氏: 当社は「包装資材事業」と「住宅事業」という2つの柱で事業を展開しています。包装資材事業では、段ボールやパレットの製造を中心に手がけてきました。さらに、包装資材事業の一環で、倉庫事業も展開。富士市内3拠点で、お客様の荷物を保管して出荷する物流サービスを提供しています。一方、住宅事業では、新富士駅北側のショールーム「キト暮ラスカ」を拠点に、地産のブランド品である「富士ひのき」を使った木造住宅を提供しています。
――川口さんと鈴木さんは「企画開発室」に所属されていますが、どのような役割を担っておられるのですか。
富士木材・川口氏: 企画開発室の発足背景からご説明すると、当社は長年、BtoB事業が主軸でしたが、「もう少し視野を広げよう」ということで、BtoC商材も企画していくことになりました。そこで約11年前、包装資材事業部の中に企画開発室を新設。ECサイトも立ち上げてブラッシュアップを続けてきています。BtoC製品の第一弾として開発したのが、「段ボール製の簡易トイレ」。お客様から非常に好評で、引き合いも多くいただいています。私がその企画開発室の室長を務め、鈴木は2024年4月に新たに加わったメンバーです。

――「デジタルツールを活用したCNFオープンイノベーション促進事業」には、どのような理由や背景で参画を決められたのでしょうか。
富士木材・川口氏: 富士市役所の方からの案内がきっかけでした。当社としても以前より「自社だけでは、今後、限界がくる」と危惧しており、他社との共創による新たな取り組みを進めてきました。そうした共創活動の中で、同じ課題を持つ会社との連携が鍵になると実感しており、ぜひこの取り組みにも参加したいと手を挙げたのです。
――すでに共創実績があるとのことですが、どのような成果につながっているのですか。
富士木材・川口氏: 自動車部品メーカーのJATCO社と共同で、アウトドア用ナイフを制作しました。JATCO社は金属の端材の処分にお困りで、当社も住宅事業で「富士ひのき」を使用していますが、廃材がたくさん発生しており、廃棄するしか選択肢がありませんでした。
そこで、刃の部分はJATCO社で、柄の部分は当社で制作し、完成したナイフをJATCO社のECサイトで販売したところ、サイトオープンと同時に完売してしまったんですね。このような結果に大変驚くとともに、大きな手応えを感じました。

▲JATCO社と富士木材の共創によって発売されたキャンプ用ナイフ 「JATCO eco-knife ARUNEMO」。(画像出典:富士木材HP)
――両社の廃材を組み合わせて新製品を開発されたのですね。今回は、どんなパートナー企業とともに、どのような事業を実現していきたいとお考えですか。
富士木材・川口氏: 今回、取り組みたいことは大きく2つです。1つ目は、デザインやアイデア面で当社に不足している部分をご教示いただきながら、自社だけでは実現できない新製品を生み出すこと。2つ目は、JATCO社との事例のように、異業種や他素材の企業と協力し、双方の素材の良さを活かした相乗効果のある製品を開発することです。
――共創で活用できる御社の強みには、どのようなものがありますか。
富士木材・川口氏: 当社の強みは、地産ブランドの「富士ひのき」をはじめ、多様な樹種を提供できる点です。特に「富士ひのき」は、水も空気も澄んだ富士山麓に生息する木ですから、香りも豊富ですし十分な強度があります。さらに、段ボールや木材に関する技術力や設計力も保有していますし、段ボールそのものの提供も柔軟にできます。
――創業110年以上ということで、長年かけて育んでこられたノウハウや技術力、設計力があるということですね。最後に、本事業にかける意気込みや応募企業へのメッセージをお願いします。
富士木材・鈴木氏: 私は「AUBA」の担当者として、募集ページの作成や企業様とのやり取りを行っています。まだどのような企業と、どうつながれるかは分かりませんが、非常に興味深い取り組みだと感じています。アイデアの実現は簡単ではありませんが、「前例がないから実現できない」で終わらせず、「前例が無い事に挑戦し実現させる」ことにシフトさせて、色々な挑戦を仕掛けていきたいと思います。

富士木材・川口氏: 当社はアイデアやデザイン、発信力に課題を抱えており、自社のECサイトも十分な成果を上げられていません。また、自社素材だけでは実現が難しい製品を、他素材との融合で形にしていきたいと考えています。今回の取り組みを通じて、そうしたつながりを築ければと思っています。興味をお持ちいただけましたら、ぜひご応募ください。

取材後記
富士市が進める「セルロースナノファイバー(CNF)」の産業化に対する取り組みは、地域経済の活性化だけでなく、環境への配慮も兼ね備えており、大きなポテンシャルを秘めていると改めて感じた。また、「富士市CNFプラットフォーム」に所属する企業では、CNFだけでなく多様な環境配慮型素材の開発が盛んで、この分野への関心の高さがうかがえる。豊かな木材と水資源を持つこの地域で、地元企業と共に新たな事業を築く取り組みは、応募企業にとっても大きなビジネスチャンスとなるだろう。
<各社の募集内容詳細や応募先は、以下をご覧ください>
●エフピー化成工業株式会社 https://auba.eiicon.net/projects/41406
●第一工業製薬株式会社 https://auba.eiicon.net/projects/41376
●日本食品化工株式会社 https://auba.eiicon.net/projects/41395
●富士木材株式会社 https://auba.eiicon.net/projects/41385
(編集:眞田幸剛、文:林和歌子・入福愛子、撮影:齊木恵太・古林洋平)