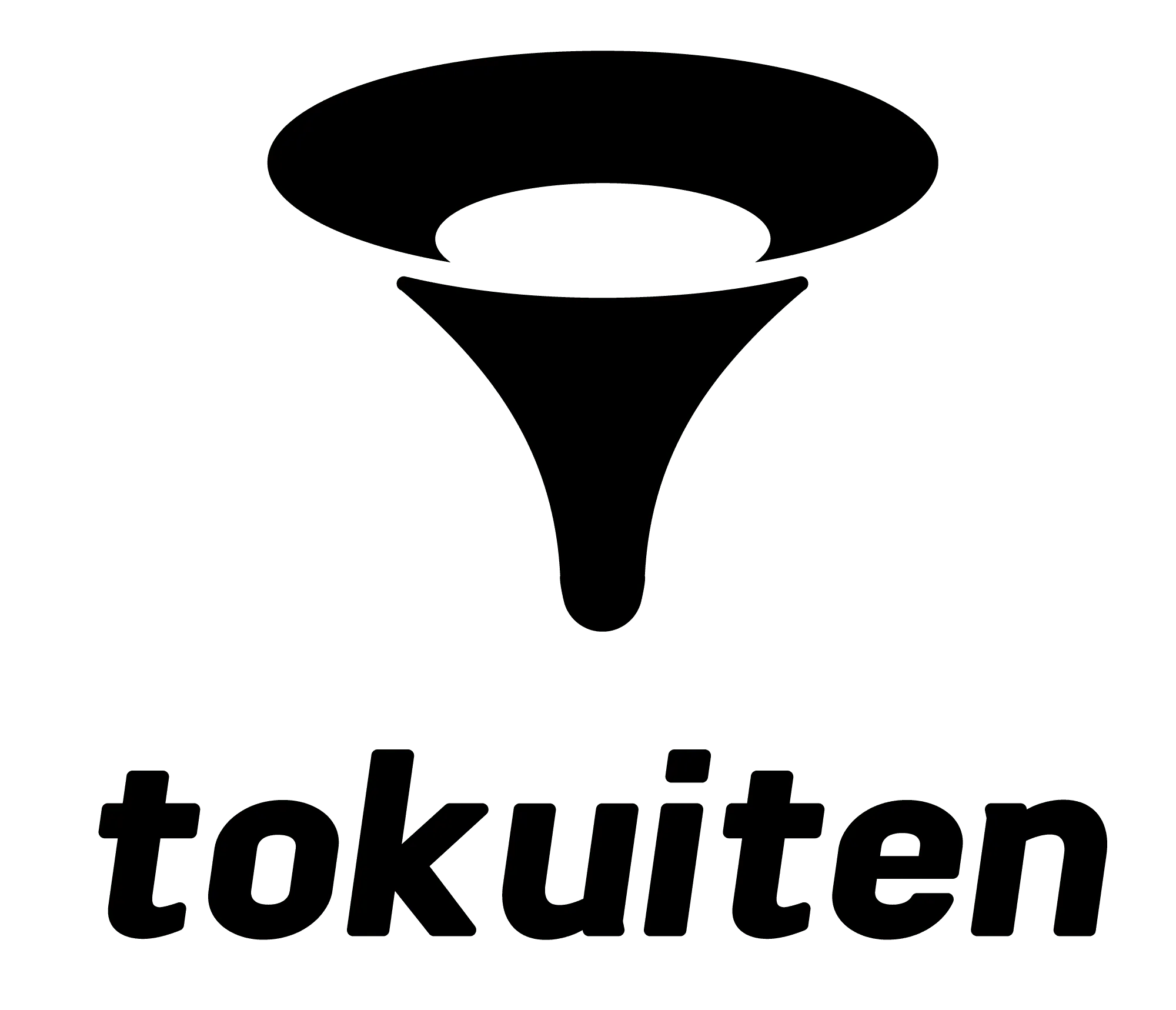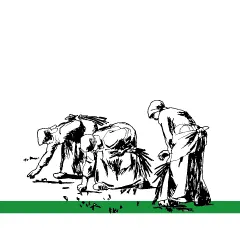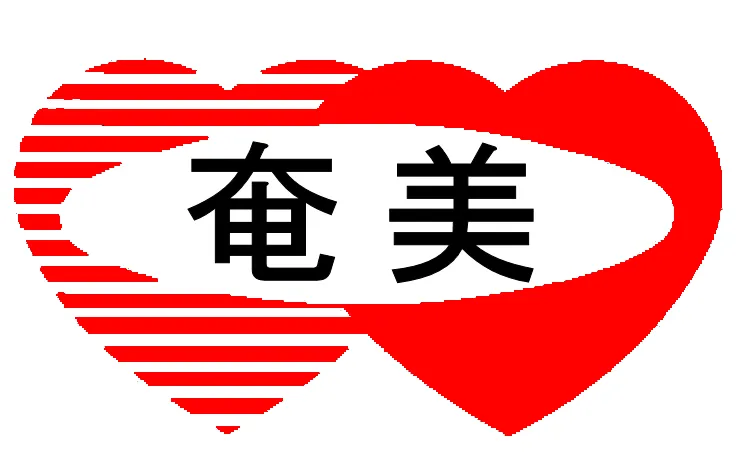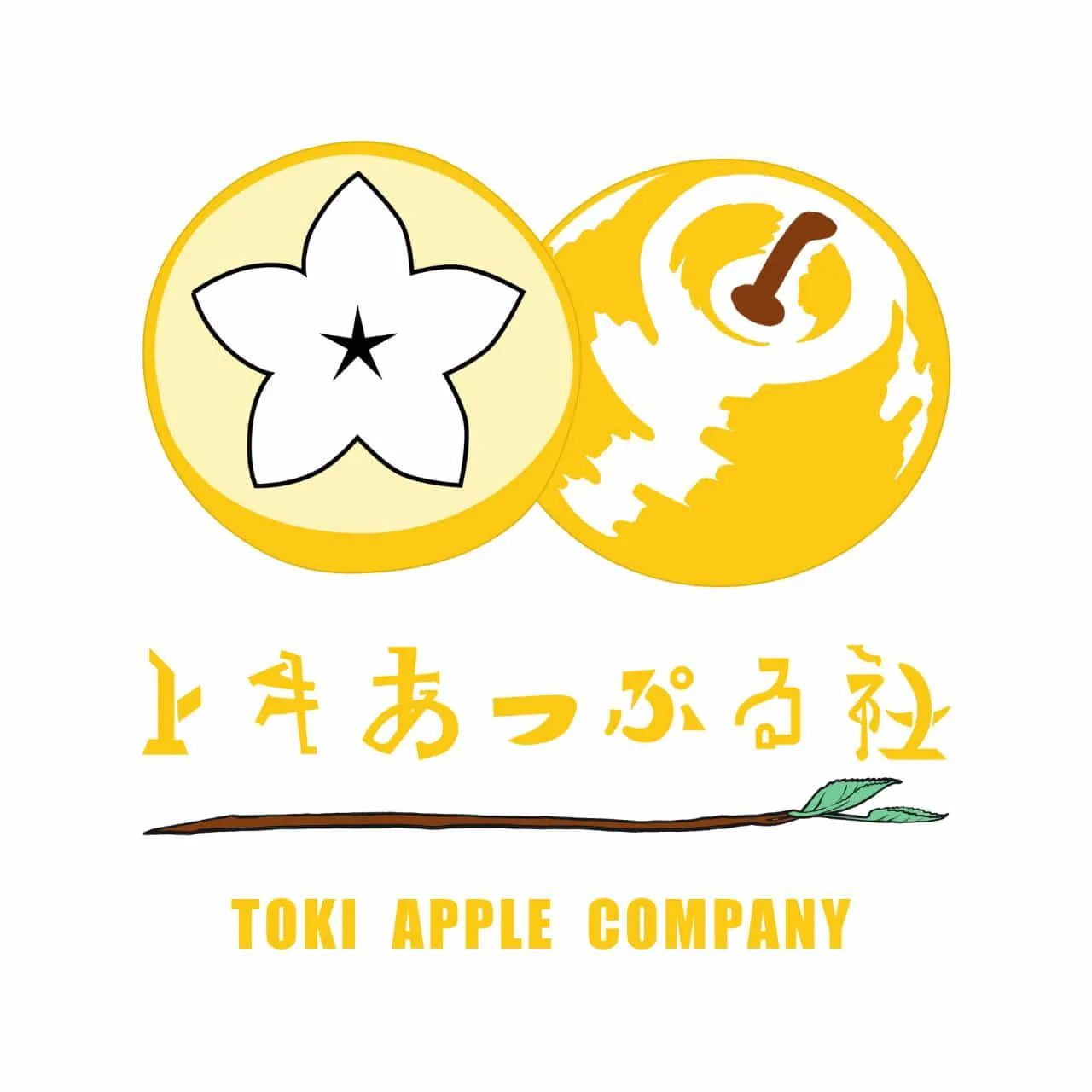- 更新:2025年09月01日
高効率な乾燥技術や酵素などを活用した中小規模製麦技術の確立による地産クラフトビール開発【渋沢MIXオープンイノベーションプログラム Canvas】
株式会社協同商事

- 飲料・酒類
- 農業
- フードロス
- 事業提携
- ジョイントベンチャー設立
- 中小企業
- 地方発ベンチャー
プロジェクトメンバー
責任者
プランのアップグレードで企業責任者情報を確認いただけます
プラン詳細はこちら
自社特徴
1975年に埼玉川越の地で創業した当社は、生産者が質の高い農産物をつくる事に専念できるよう、物流、包装加工、営業等をワンストップで行う支援する有機農産物の専門商社が祖業です。
農産物の栽培から、物流、販売、食品への加工を含め、農産物がお客様に消費されるまでのすべての過程を農業の一環と考え、有機栽培青果物栽培・加工・販売、物流、ビール醸造、廃棄物リサイクル技術研究開発等、農業を出発点とする食品のサイクルすべてに関与するアグリベンチャーとして活動しています。
1996年、川越地域の農産物の有効活用を着想の原点として、ビール製造に進出しました。COEDO BREWERYというブランドで、川越産のサツマイモから製造した「紅赤-Beniaka-」を筆頭に、日本の職人達による細やかなものづくりと「ビールを自由に選ぶ」というビール本来の豊かな味わいの魅力を、武蔵野の農業の魅力とともに発信してきました。日本全国での流通の確立、そして世界30か国への輸出実績を有しています。
クラフトビール黎明期より、ビールの本質的価値をコミュニケーションするモノ・コトをデザインし、ビールを媒体として、地域や農業の魅力や関わりを提供しています。
提供リソース
醸造所敷地内農地:大麦の試験栽培区画
イベント・試飲会場:音楽祭やキャンプなど地域イベント拠点として、醸造所6haの敷地の利用が可能
販売チャネル:コエドビール直営店舗・オンラインストア・食品卸を通じた量販店への営業コンタクト
R&Dサポート:醸造家、品質管理、大学/企業間連携窓口
地域ネットワーク:地元農家、観光協会、学校、メディア連携
マーケティング力:「コエド」ブランドによるPR・販促支援
解決したい課題
【テーマ①】
効率的な乾燥技術構築による中小規模製麦の確立
洗浄・浸漬・乾燥に至る効果的なプロセス設計や、高効率に稼働する乾燥機の設計による中小規模製麦生産体制を実証します。
【テーマ②】
麹由来の糖化酵素を活用したビールに最適化した大麦の糖化方法の確立
麹菌を利用し、ビール製造に適した大麦のデンプンの糖化の可能性を模索します。従来の麦芽製麦工場によらない、麹菌の働きを活用した糖化技術を確立し、日本産クラフトビールのプレゼンスを世界でも高めることができるような独自の製法を共同開発します。
■詳細・応募はこちら:チケット消費なしhttps://shibusawamix-canvas.eiicon.net/theme/prefecture/kyodoshoji
※ページ右上「応募する」ボタン:
プログラムへの応募はこちらからも無料で可能です。(チケット消費なし)
※ページ右上「メッセージを送る」ボタン:
プログラムについて個別の提案・相談がある際は、ご連絡ください。(チケット消費あり)
すべての企業様と個別面談に対応できない場合がありますこと、ご了承くださいませ。
共創で実現したいこと
国産ビールは原材料の8割が輸入麦芽である現状を打破するため、東松山の醸造所敷地内で栽培した大麦を自社で製麦できる技術・体制を構築します。
香味・甘味・発酵適性に優れた地産麦芽を製造。
休耕地の有効活用とあわせて、地元や国内のマイクロブルワリーとの連携で国産クラフトビールの新しいサプライチェーンを創出します。
求めている条件
高効率に稼働する乾燥体制の構築が行える企業
プロセスモニタリング&最適化技術を持つ企業
低温・真空乾燥技術を持つ企業
麹酵素活用による麦芽化プロセスの実証実験が可能な企業
オープンイノベーション実績
▽コラボレーションによるオープンイノベーション事例
25年 NEC:人生醸造craft(Aiとビール職人の共創)/ 24年~現 信州大学×飯綱町:香琳-Kourin-(飯綱町産の授粉用林檎を信大の特許技術で糖蜜液を抽出、ビールの原材料として採用)/ 19年~現 堀口珈琲:ブルワー(ビール職人)とロースター(焙煎職人)による新たな味わい体験の創造 / 22年~24年 Y'sコネクションと農を起点としたキャンプ型音楽フェス「麦ノ秋音楽祭」を醸造所の敷地内を活用、実施等
企業情報
- 企業名
- 株式会社協同商事
- 事業内容
- 弊社は1975年より有機野菜の卸売業を埼玉川越の地で創業し、生産者さんが質の高い農産物をつくる事に専念できるよう、加工、物流、営業等をワンストップで行う専門商社が母体となっています。 農産物の栽培から、物流、販売、食品への加工を含め、農産物がお客様に消費されるまでのすべての家庭を農業の一環と考え、有機栽培青果物栽培・加工・販売、物流、ビール醸造、廃棄物リサイクル技術研究開発等、農業を出発点とする食品のサイクルすべてに関与するアグリベンチャーです。 96年、川越地域の農産物の活用がビール事業における着想の原点となります。COEDO BREWERYというブランドで日本全国、世界30か国への輸出実績を持ちます。クラフトビール黎明期よりビールの本質的価値をモノ・コトを通じたコミュニケーションをデザインし、ビールを媒体として地域や農業の魅力や関わりを提供しています。
- 所在地
- 埼玉県川越市中台南2-20-1
- 設立年
- 1982年
プランのアップグレードで企業情報をご確認頂けます
プラン詳細はこちら